壱
弐
参
小狐丸
2017年3月24日
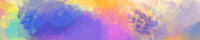
不意に口の中に指を差し込まれた。彼の爪は鑢で丸く整えられているから彼女の口内を傷つけることは無いが、これでは喋ることは疎か呼吸もままならない。長い指が上顎を擽り、頬の内側を撫で、舌を掴む。苦しさに涙目になりながらも見上げると「嘘はいけませんよ、ぬしさま」と狐は赤い目を細めて笑う。
小狐丸
2017年3月24日

あの頃の小狐丸は彼女の手に触れることが史上の歓びだった。その小さな手以外にも触れたいと思わない訳では無かったし、触れようと思えば触れることはできた。艶めく髪にも、柔らかな頬にも、桜色の唇にも。だが、まだもう少しだけ、この溶けそうなほど熱い心地よさと戯れていたいと、そう思っていた。
燭台切光忠
2017年7月28日
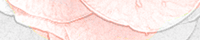
おかえりなさいと微笑んで、彼の上着を受け取り、きっちり結ばれていた黒いタイに手を伸ばして解く。「これくらい自分でできるのに」と彼は苦笑するが、やめてなんかあげない。これは私のしたいことだ。部屋着に着替えた彼の胸に飛び込んで、大きく息を吸い込んで、キスをする。これも私のしたいこと。
岩融
2017年7月28日
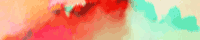
「あたたかい」がわからないのだと彼は言う。成る程確かに、鉄でできた彼ら刀剣男士は熱い冷たいを感じることはあれ、心地よい温度を味わうことはなかったのだろう。ならばと彼女は冷たい川のせせらぎに手を浸す。そうして彼の頬にその手を寄せた。「良い?これが冷たい。そしてこれが、
膝丸
2017年7月28日

大丈夫だから、と彼女はいうものの、器用ではないくせお転婆な彼女を心配せずいるのは到底無理な話だ。「ほら、そんなに慌てては、転けてしまうぞ」「その時は、支えてくれるんでしょう?」そう言って彼女は革靴と靴下を無理やり手渡してくる。すべすべのつま先が白い砂浜に触れる。
小狐丸
2017年7月28日

淡い色のその髪の毛を撫でるようにさらさらと梳る。この細く艶々とした糸で機を織れば絹よりも滑らかな生地が出来上がることであろう。そのような布に出会うことはおそらく一生有り得ないだろうけれど。「ごめんね」と呟いて鋏を握る、その手はぶるぶると震えていた。
小狐丸
2017年7月28日

溺れる、とは、水中に堕ちて浮き上がれなくなることをいうのだと思っていた。が、今の彼女は色とりどりの花に溺れてしまいそうだと思う。風が吹いて、花弁が舞い上がり、その姿が霞む。早く救い出さねば。
「救うのは無理だよ。その花は貴方だもの。彼女は貴方に溺れている」
小狐丸
2017年11月12日
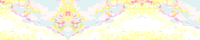
小狐丸が戦場に赴くと、雨が止み雲の隙間から太陽が顔を見せるのが常であった。そのため、衣を濡らして帰城する事は滅多に無い筈だが、本丸に戻った彼の黄金は変色し水分を吸ってずっしり重い。「返り血です、心配はいりませんよぬしさま」彼女の瞳から溢れた水がぽたり一雫落ちて、また着物が濡れる。
小狐丸
2017年11月12日

くらりと世界が揺らぐ。あ、倒れると思い身を固くしたが、想像したような衝撃は体に伝わってこない。代わりに触れたのは暖かな体温。「ぬしさま、お怪我はございませんか?」お姫様抱っこをしましょうか?と聞かれ、大丈夫と立ち上がりかけたが思い直しその袖を引く。今日は彼の好意に甘えてしまおう。
小狐丸
2017年11月12日
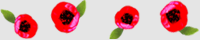
振り返ると赤い二つの宝石がすうと細まり「ぬしさま」と微笑みかけてくる。審神者会議が開かれる会館の上りエスカレーターに乗る時はいつも小狐丸は彼女の背を守るように後ろに立つ。彼と同じ目線になれるのはこういう時くらいだから、あぶないからと何度注意されてもつい後ろを振り返ってしまうのだ。
大倶利伽羅
2017年11月12日
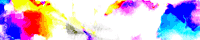
「あ、」声がした方を見ると彼女が困り顔で立ち止まっていた。「ごめんなさい大倶利伽羅さん、少し待っててもらえますか?」どうやら洋服の背についた結い紐がほどけてしまったらしい。暫く立ち止まっていたが、背中側になかなか手が届かず手間取る彼女に痺れを切らし、その後ろに立つ。「貸してみろ」
岩融
2017年11月12日

あまりにも小さな背だと思う。彼女は「岩融程じゃないけど、鍛えてるしその辺の女子より大きいと思うよ」と笑うが、その双肩にかかる重さに見合った広さでないと彼は思うのだ。「主よ、全て奪うわけではない。少しで良いから俺に預けてくれないか」きっとそう言っても彼女は大丈夫だと微笑むのだろう。
小狐丸
2017年11月16日

慌てて彼の元へ向かうと「そのように急いでは危ないですよ、お気をつけくだされぬしさま」と狐は微笑む。だが今は全くそれどころでは無いのだ。できたばかりの傷にそっと手をかざす。「小狐丸ちゃん」「はい」「小狐丸ちゃん」「私はここにいますよぬしさま」彼の痛みを全て肩代わりできればいいのに。
小狐丸
2017年11月16日

寒さは得意なのだと彼は言う。冬に餌を狩る獣ゆえ、下がる気温もちらつく雪も気にすることなく舞い踊ることができるのだと。対して彼女は寒さに弱く、師走は少し先だというのに居間の炬燵から離れることができないのだと言う。「でしたらぬしさま、もう少し小狐めのお側へ」少しは暖かくなるでしょう?
小狐丸
2017年11月17日

「大きい釜があれば甘栗を作りたいのですが、本丸の台所では難しいですね」と言いながら、彼女は囲炉裏炬燵で焼いた栗の皮をぶかぶかの軍手をつけた小さな手でポロポロと器用に剥いていく。「小狐丸ちゃん、」名前を呼ばれ促されるままに口を開ける。秋の果実のほくほくとした甘さが、口中に広がった。
小狐丸
2017年11月20日
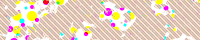
先刻まで晴れていた空に急に雲がかかり、ぽつりぽつりと雫が落ち始めた。彼女は慌てて立ち上がり、部屋を出る。案の定、彼は庭で一人空を見上げ佇んでいた。戦の成果が芳しくなかった時はいつもそうだ。「小狐丸ちゃん」名を呼ぶ声が雨音に消える。せめて彼の側にいようと彼女は雨の中一歩踏み出した。
小狐丸
2017年11月21日

彼の頭上で跳ねる白い毛の手触りが今日は一際良さそうで、朝からずっと触りたいと思っていた。が、彼の背は高く、頂にはとても届かない。爪先に力を込め背伸びすると、同時に彼も身を屈め、何か言う前に唇に柔らかい物が触れた。「このようにしたかったのではないのですか?」笑う狐は実に楽しそうだ。
小狐丸
2017年11月22日
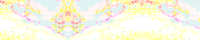
「狐はつがいの雌に尽くすものなのですよ、ぬしさま」と小狐丸は甲斐甲斐しく彼女の世話を焼きたがる。私がしたいからしているので気になさらずとも良いのですよと彼は言うが、それでは気が収まらない。「私も小狐丸ちゃんに何かしたいし、何かを捧げたいんです」そう言うと狐は嬉しそうに目を細めた。
小狐丸(今剣視点)
2017年11月22日

人と刀剣男士の夫婦とはどのようなものなのだろう。今剣は思案する。人の”夫婦”と似ては似つかぬ結びつき。どのような形になるかは、本人達次第だ。庭の紅葉の最後の一つが落ちる夜、彼の主とその近侍は契りを結ぶ。彼等が紡ぐその糸は、夫婦の真似事であろうか、それとももっと別の何かであろうか。
小狐丸
2018年1月2日

小狐丸は海の向こうの香辛料が得意ではないらしい。香りが嫌いという訳ではないようだが、舌がピリピリとする感覚が苦手なのだろう。厨番に伝え香辛料を抜いてもらう事もできるが、「ぬしさま、口直しをさせてくだされ」と狐が手招きをしてくるのが嬉しくて、この事は審神者だけの心にしまったままだ。
小狐丸
2018年1月2日

キラキラと太陽を反射する嫋やかな白髪に対し、彼のまゆげとまつげは漆黒の闇の色だ。「全然違う色なのに、不思議ですね」そう言ってサラサラと毛並みを整えてやると狐は嬉しそうに目を細めて笑う。「決して不思議なことではないのですよぬしさま、黒い私も白い私もどちらも私、どちらもぬしさまの物」