壱
弐
参
へし切り長谷部
2015年3月16日

長谷部は審神者にとって初めての刀剣ではなかったし、おそらく長谷部にとっても審神者は初めての主ではなかった。長谷部には長谷部自身は気づいていないかもしれないが前の主の影響が色濃く残っていたし、審神者も以前に近侍であった刀剣と長谷部では勝手が違い戸惑うことが多くあった。だからこそ、こうして触れたいと思うことが不思議でたまらない。
前の彼には、そのようなことは思わなかったのに。
「初めてです。刀剣と…いえ、人とこのようなことをするのは。」
「奇遇ですね、俺もこのようなことをするのは主初めてですよ。」
手を伸ばす時指が震えるのも、目の前のその人以外目に入ってこないのも、初めてだから戸惑いが隠せない。
岩融
2015年3月16日
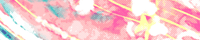
「アヤメの花、だな。」
岩融という『人』は、審神者が思っていた以上に品があり、知識も教養もあるらしい。審神者が本丸の庭で育てている花に関しても心得があるらしく、これまで、審神者が育てている花の名前を香りだけで言い当てたことは多々あったし、今も球根を見ただけでこの花の名前を言いててしまった。それに、彼に投げかけた問いにはいつも丁寧な答えが返ってくる。だから、というわけではないが、彼には独り善がりな質問を投げてみたくなるのだ。
「どうして、この花を育てているか、わかりますか?」彼は、言い当てることができるだろうか。その袈裟によく似た色の花だから選んだのだと。
鶴丸国永
2015年3月16日

驚くことができないのだ、と審神者は言う。感情が無いというわけではないらしい。ただ、鶴丸がいくら彼女の心臓を大きく動かそうとしても、彼女は少し笑うだけで、目を見開きもしないのだ。
だが、鶴丸が自ら単独で敵の本陣に入り重傷を負ったと聞いた時は流石の審神者も驚いた、というよりも肝が冷えた。鶴丸曰く、こうすればその表情が見れるんじゃないかと思ったのだと。「そういう方法は、酷いと思います」震える声で言う審神者を見て鶴丸は「でも、驚いただろう?」と楽しそうに笑い、その指で審神者の目に浮かんだ涙を拭った。
薬研藤四郎
2015年3月16日

「俺は大将となら何処へでも行くぜ。」いつもそう言って薬研は笑う。それが頼もしくもあり、愛おしくもあった。彼と一緒なら、死ぬのだって怖くない、そんな気がしたのだ。だが、その審神者の思いは薬研自身に見事に打ち砕かれる。
「薬研、薬研、お願い、」
「残念だが、そっちへは大将の頼みでも行けそうにないな。」
何故、とか、どうして、とかを審神者が言葉にする前に、彼は人差し指で彼女の口を塞ぎ、「もちろん、あんたもそこへは行かせないぜ。大将。」と笑った。
あんたを死なせはしない。そう、力強く手を握られ、嗚咽を漏らすことしかできなかった。
歌仙兼定
2015年3月16日

歌仙兼定は文系である。雅と風流をを愛し、和歌や茶道を好み、計算ごとは苦手、らしい。
とはいえ、彼はかなり剣の腕が立つ。審神者には剣術も武術もよく分からないが、戦場において彼が最も活躍している刀剣であることは確かだ。
その日は歌仙以外の刀剣のほとんどが隊に配属されて間もない新入りばかりだった。いつも通りに進まない戦闘に、審神者にも焦りや苛立ちがあったのも確かだ。危ないのではないか、と歌仙はやんわりと静止したが、無理に進軍をした。結果、歌仙は軽傷で済んだものの、他の刀剣たちは大きな傷を負って帰ってきてしまった。
他の物の手入れが終わるのを大人しく待っていた歌仙だが、審神者と二人きりになり手入れを始めると、不平不満が口から出てくる。
「だから言ったじゃないか。彼らにはあの戦場はまだ早すぎる。」
「ごめんなさい歌仙。あなたが頼りになるから、つい無理を言ってしまいます。」
こうしてぶつぶつと文句を言いつつも、彼は審神者を支え、守ってくれる。歌仙兼定は文系である。