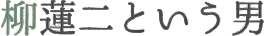柳蓮二に関する短編集です。
立海大附属中は、海からほど近い場所にある。
必然的に、男女の逢引は海岸で行われることになるし、この海岸を制服を着た男女が二人きりで歩いていたら、恋人同士と見て間違い無い。
そして今、私と柳蓮二はその海岸を二人きりで制服を着て歩いている。ということは、私たちは恋人同士ということになるのだろうか。そうではなくても、そのように他人から見られているのだろうか。
でも、柳も私もとくに何も喋らないし、手をつないだり腕を組んだりすることもない。ただ歩いて、考え事をして、歩いて、の繰り返しだ。これでは恋人同士とは言えないのではないだろうか。
そもそも恋人同士とはなんだ?
「随分と哲学的な質問だな。」
「哲学的?」
「学問では答えられないような質問だ、ということだ。」
「哲学的な話はきらい?」
「いや、お前がそんな話をするとは思わなかっただけだ。まだまだ、データ不足だな。」
そう言って柳は少し笑う。あたらしいおもちゃが手に入った時の子供の顔に似ている。柳のそのような顔が見たくて、私は柳のデータを裏切るような行動をしたくなる。
「柳といるとね、こういうこと話してみたくなるの。頭が良い人のふりをしてみたくなるの。」
「頭が良い者は『恋人同士とはなんだ』とは聞かない。」
「それもそうだね。」
こうして柳と話をしながら、海岸を歩くのは嫌いじゃない。嫌いじゃないけど、どきどきしたりせつなくなったりするわけじゃないから恋じゃない。
私が柳に向けているのは、それこそ学問では定義できないような感情で、こうして砂を踏みしめる度にその答えを考えているのだけれど、明確な回答は未だにわからない。
「、」
「なに?」
「もう一往復したいのだが、構わないだろうか。」
「……いいよ。」
こうしてまた、私たちは特に意味もなく海岸を歩く。
私たちが恋人同士なのかそうでないのかは自分でもよく分からないし、たぶん柳も分かっていないのだろう。けれど、こうして歩くうちに、答えが見つかるのではないか、という気がする。
見つからなくてもそれでいいのかもしれない。私たちが歩くことに変わりはないし、波の音は穏やかだ。
柳は私のことを何でも知りたがる。いや、彼が知りたがるのは私のことだけではないのだけれど。データマンである彼は、私が自分で意識していなかったような癖や習慣まで、言い当ててくるから、少し怖い。
だけど私は、彼のことは何も知らない。彼の普通のクラスメイトが知っている以上のことは、分からないのだ。彼の所属するテニス部のマネージャーなのに、情けないと思う。
ただ、彼みたいに先の行動が読めてしまうようなデータや、何でも見抜いてしまうような洞察力は私には無いから、彼の深いところを彼の口から教えてほしい、とひそかに思っている。

そんな柳が部活中に倒れた。ふらりと音もたてず。普段から人一倍体調に気を使ってをデータ管理しているにもかかわらず、だ。
どうやら風邪をひいたらしい。彼を保健室に引きずり込み、ベッドに寝かせる。熱を測ってみるとかなりの高熱だ。
かしこい人は自己管理もしっかりしている物と思っていたが、どうやら彼は”この程度なら大丈夫”というラインが分かってしまうためそのぎりぎりまで無理をしてしまうらしい。
養護教諭が不在のため、棚に置いてあった救急箱から冷却シートを引っ張り出し、柳の額に貼りつけた。”柳に雪折れなし”という言葉があるが、折れなくても倒れてしまえば結果は同じである。
「ということは、朝から体調は万全ではなかったってことだよね?」
「その時はまだ大丈夫だった。」
「大丈夫じゃないから、今ここで寝てるんでしょ?」
「しかし……」
”でも、だって”という子供のような言い訳する柳を、保健室の来室記録を書きながら、問い詰める。
「柳はいつもそう。大事なことを私に教えてくれない。」
「教えているつもりだ。」
「それって、テニスの練習や試合のことでしょう。そういう事だけじゃなくて、柳の弱いところも教えてほしいの。」
少し沈黙が流れた。薄く開かれている涼やかな彼の瞳を真っ直ぐ見る。目をそらしたら、負けだと思った。
しばらくして、根負けしたのか、柳はふぅ、と溜息をつき、笑う。
「……そうか、そうだな、なら一つだけ、良いことを教えよう。」
「良いこと?」
「俺の弱いところだ。」
「柳の、」
そうだ、と柳は頷く。
まさかここで、柳の弱いところが聞けるとは思わなくて、慌てて姿勢をただした。座っているベッドの横のパイプいすがぎしりとなる。
そんな私の手をそっと握り、柳はゆっくりと口を開いた。
「……俺は、お前に弱い。」
そう言ってから、柳はまた少し笑った。
「はぁ?」と間抜けな反応しかできなかった。私に弱い、とは、つまり、私が考えている通りの解釈でいいのだろうか。
思考停止する私をそのままに、彼は「そのうちわかるようになる。」と体を起こし、テキパキと救急箱を片付け始めた。
慌てて私も立ちあがり、「寝てなさい!」と彼を一括し、救急箱を奪い取る。あぁもしかしたら、私のおでこにも冷却シートが必要かもしれない。
新しくマネージャーとしてテニス部に入ってきた女の子は、まさに”先月まで小学生でした”というような風貌をしていた。
細くて、小柄で、力も弱そうで、二・三年生だけでなく一年生までひやひやしながら彼女がドリンクを運んだり練習の記録をとったりするのを見守っていた。
しかし周りの心配をよそに、彼女は仕事をテキパキとこなし、稀に背丈や体格のせいでできないことがあっても、良く笑い良く喋るから周りの者からとても好かれたため、誰もが率先して彼女のことを手伝った。
そんな彼女を見て、柳蓮二は思う。この小さな女の子を、自分の好きなようにしたい。
そういったドロドロした感情を向けて良いような相手ではない、ということは分かっている。
しかも、彼女ら一年生にとって自分たち三年生は随分と大人に見えるようで「柳さん、柳さん」と、とても頼りにされる。体が大きくなり力が強くなっただけで、思考はあまり成長していないというのに。
恐らくそのような目で、彼女を見ている部員は少なくないだろう。ちいさくかわいらしい上、時折信じられないほど女っぽい仕草を見せるのだ。そこがたまらなく愛おしかった。

マネージャーは晴れた日はたいてい洗濯に追われている。それを見越して柳は水場のそばで待ち伏せをし、彼女に声をかけた。
「、洗濯か?」
「あ、柳さん。」
籠いっぱいの洗濯ものを抱えて彼女は「お疲れ様です」と軽く会釈をした。自然な動作で、柳はその籠を引き取る。
「もう慣れたか。」
「はい、ありがとうございます。」
「いつもすまないな、」
他愛のない話をしながら「あそこへ」と彼女が示した部室の裏に二人で並んで向かう。こうしているうちに、彼女が自分なしではここに居られなくなればいいと思っていた。
洗濯物干しに使っているロープが張ってある付近にたどり着くと、彼女はぺこりと頭を下げ「柳さん、練習は?」と聞いてきた。
「今日は試合形式だからな。もうしばらく手が空いている。他に何か手伝うことは…、」
「じゃあ、…このタオル、あの上にほしてもらっても良いですか?」
あの上、と彼女はロープの上の方を示した。
柳は「あぁ、」と頷き、タオルをロープにかけ、そして気付く。彼女を自分のものにするつもりが、自分が利用されているではないか。
視線を落とすと、彼女は楽しそうに他の洗濯物をロープの下の方に干している。我ながらなかなか手ごわい相手に目をつけてしまったようだ。
「横浜駅まででいいか。」
「うん。」
いいか、と聞きつつ、疑問形でなく断定系だ。『彼』はいつもそうだ。私の思っていることを先回り先回りして、口に出してくれる。
口下手な私にとってそれは楽ではあるけれど、少し窮屈に甘やかされているような気分にもなる。
車を運転する男性の横顔はかっこいいと思う。『彼』はいつもかっこよくてやさしいのだけれど。
こうして私の自宅から駅まで、タクシー代わりをしてくれる男性なんて、他にはいない。
「あいつは元気か。」
「…最近会ってないからよくわからない。」
「…そうか。」
『彼』はいつもそうだ。彼の幼馴染である『あの人』のことを聞いてくる。その質問にいつも、私は明確な答えを返せない。恐らく『彼』はそのことまで予測済みなのだろう。恐ろしい男だ、と思うが、そんな『彼』のことが嫌いではない。

目的地の近くに差し掛かったころ、『彼』のスーツのポケットの中の携帯電話が着信を告げた。聞きなれたベルの音が2回、3回、と続く。
「出なくていいの?」
「運転中だしな。」
それもそうだ、と納得し、座り直し前を向く。携帯電話はもう何度かベルを鳴らして、音は止まった。
車内は一気に静かになる。『彼』はいつもそうだ。駅の近くになると、口数が少なくなる。
窓を打ち付ける雨の音と、ワイパーのゴムの音しか聞こえない。窓の外のビルの明かりがじんわりと溶けて、とても綺麗だ。

地下の駐車場から駆け足で改札へ向かう。
近くに海が見える駅の東口、そこに『あの人』は居なかった。
「!」
名前を呼ばれる。聞き覚えのある声だ。でも『あの人』の声じゃない。
「……、蓮二は…、」
「いいよ、貞治。何も言わないで。」
『彼』は、乾貞治はいつもそうだ。私の思っていることを先回り先回りしても、結局何もできないことがある。
『あの人』は、柳蓮二はいつもそうだ。私に思っていることを何も言ってくれない、とても意地悪だ。
私はいつもそうだ。『あの人』よりもっと意地悪で、隣に居る『彼』に、涙を拭わせる気すらない。