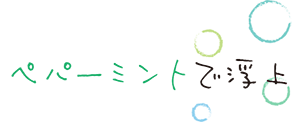好きな人に、告白された。
それは私にとってすごく衝撃的なことで、想いを告げられ、思わず「ドッキリ…?」とつぶやいてしまった。
だって彼は、明らかに女の子に興味がなさそうだったし、…それどころか男の子に興味があるみたいだったし、私のことなんか眼中にないんや、とおもってた。
それでも彼は、「それとこれとは話が別や!」と言い切り、彼女にしたいと思うのはお前だけやと言ってくれた。
その人の名前は、一氏ユウジという。

とはいっても、『彼女にしたい女子』が私だっただけで、『世界で一番好きな人』が私というわけではないようだ。
一氏の告白は勿論二つ返事でオッケーして、その次の日、校門の前で偶然会って、ぎこちなくあいさつした後は、「いくで」と私の手を引き迷いなく世界で一番大好きな金色小春ちゃんの元へ。そうしていつも通り、小春ちゃんと話し始めた。それでも手だけはちゃんと私の手とつながったままで、嬉しいけどこっちを向いてほしくて、複雑な気分だ。
それも、最初のうちだけかな、とも思ったけれど、彼の告白から数週間たってもそんなかんじ。まあ一氏の、小春ちゃんに対してはデレデレだけど他の人にはさっぱりなところに惚れたのだから、そのままで全然構わないのだけれど、そんな私たちを見ている小春ちゃんに「ごめんな、ユウくんあんなやから、大変やろ?」と気を遣わせるのはどうかと思う。「でも本当に、ユウくんはちゃんのこと好きなんやで?」と彼のフォローをする小春ちゃんに向かって、私は力強く頷いた。
「大丈夫だよ、一氏がそういう感じなんやって、前から知ってたし、私はそういう一氏が好きだから。」
心配してくれる小春ちゃんに、そう返すと、彼…いや、彼女はちょっと困ったような顔で「ありがとうね、ちゃん。」と穏やかに笑った。
そうやって、小春ちゃんと二人で話をしていると、いつも一氏が「浮気か、死なすど。」と機嫌が悪そうな顔をしながらやってくる。
その『死なすど』はどちらに向けた言葉なんだろうか。聞いてみたいんやけど、聞くのが怖くて、聞けないままだ。
「あら、ユウくん。」
「一氏、」
「何話しとんねん、お前ら。」
「ガールズトークくらいええじゃない、ねえちゃん。」
こちらを見てかわいく首をかしげる小春ちゃんを見て、私は曖昧に笑って頷くことしかできない。
「ところで小春、次のステージ衣装なんやけど…」
「はいはい、」
「あ、じゃあ私はこれで…」
一氏と小春ちゃんががお笑いのことを話そうとしていたので、私は立ちあがって教室を出ようとした、が、一氏が「ちょお待ち。」と、私を引きとめて、何かを差し出してきた。
「これ、衣装の端切れで作ったヤツ。お前にやるわ。」
「え、いいの!?」
一氏がくれたものは、鮮やかな緑色の柔らかい布でできたシュシュだった。教室の窓から差し込んでくる夕陽が反射して、飾りのスパンコールがきらきら光っている。
彼の表情を見ようとしても、照れくさいのか、窓の外に視線を向けて、こちらを見ようとはしなかった。
「やるって言うとるやろ。……あとな、別にここに居て練習見て行ってもええんやで。」
「本当に!?」
「まあ、観客がおった方が感覚がつかみやすいしな。」
そう言って、一氏はこっちを見ないままではあったが、私の手を引いて、もと座っていたところまで導いてくれた。
彼に認められたような気がして、嬉しくて、誇らしくて、飛び跳ねたくなるのを必死で堪えながら、私は教室の椅子に座りなおす。
喜ぶ私と、ぶっきらぼうに遠くを見る一氏を見て、小春ちゃんは「素直じゃないわねえ、ユウくんは。」とクスクス笑った。

その日は午後から雨で、傘を忘れた私は一氏か小春ちゃんどっちかが置き傘してへんかなあ、とか考えながら退屈な6時間目の古典を乗り切った。
二人は明日開催される毎年恒例の校内のお笑いグランプリの予選に出演するのだと張り切っていた。今日は明日の本番に向けて最終調整だ。練習から小道具作りまで、準備をずっと見てきて、私も例年以上にそのイベントがたのしみでたまらなかった。
「さん、」
授業が終わり、教科書等を片付けていると、同じクラスの女の子に声をかけられた。小柄で、かわいくて、週末のお笑いの公演でも良く見かける子だ。「なに?」と返事をすると、目を細めてにこりと笑う。
「ちょっと話があるんやけど…ホームルーム終わったら理科室に来てくれへん?」
とくにことわる理由もないので頷くと、彼女は「じゃあ、またね」と自席に戻って行った。
理科室に入ると、彼女だけでなく、数人の女の子達が待っていた。私が中に入り、ドアを閉めたのを確認すると、先刻声をかけてきた彼女がゆっくりと口を開く。
「単刀直入に言うとね、ユウジに近づかんでほしいの。」
「え?」
一瞬、何を言われているか分からなかった。キッと睨まれ、強く肩を押され、ふらつき、床に尻もちをついてしまう。
「だからね!あんたがどういうつもりなのか知らんけど!ユウジのこと好きなのはあんただけじゃないし、あんたがユウジのそばにいると不愉快だって言いたいの!消えてほしいの!二度とユウジの前に現れないでほしいの!」
捲し立てるように言われて、何も言えなかった。彼女の後ろで取り巻きのような女の子達が「ほんとそーやねえ。」とか「好きな人のこと一人占めにされてアイちゃんかわいそー、」とか言ってるのがぼんやりと聞こえる。
わかってるつもりだった。一氏は、大勢が見ているステージに立つような人で、人気者で、ファンの女の子も多いんだって。
…いや、わかってるつもりで、わかってなかったんだろう。一氏のことを、男の子として好きなのは、私だけだと思ってた。特別な気持ちで見てるのは、私だけだと思ってた。
「ちょっと、聞いてんのあんた!ユウジに近づかないでって言ってるの!」
「……聞いてるし、よくわかった。わかったけど、嫌だ。」
「はぁ!?」
立ちあがり彼女の眼を見る。背は私の方が少し高い。
「そりゃ、私よりあんたの方がかいらしいし、オシャレやし、男の子にもてるやろし、私に勝ち目なんかあらへんわ。」
「だったら…!」
「でも、誰になんと言われようと、私は、一氏のこと、好きだし。譲るつもりない。」
パンッと音がして、頬に電流が走った。
ああ、ぶたれたんだ、とどこか他人事のように思う。じんじんと痛む頬に手を当てながら彼女を見ると、彼女の手には見覚えのある緑色が握られていた。
「どうせこれも、ユウジからもらったんやろ。」
いつのまにか、髪の毛を結んでいたシュシュがむしりとられていた。彼女は心底憎々しいというふうな表情でそれを一瞥して、窓から投げ捨てた。
そこからどうやって理科室を出たのか覚えていない。気づいたらいつも一氏や小春ちゃんと3人で過ごす教室にたどりついていた。
小春ちゃんは生徒会の仕事だろうか、一氏がひとり下を向いて黙々と裁縫仕事をしながら待っていた。
「おう、お前か。じつはこれな、明日小春につけてもらおうと思っ…」
私は相当酷い顔をしていたのだろう、顔を上げた一氏はぎょっとして言葉に詰まり、それから恐る恐る「大丈夫か?」と声をかけてきた。
「おまえ、その顔、誰に…、」
「べつになにも。」
「べつになにもって……。めっちゃ手形ついてんで?」
「なんでもあらへんって。」
言えるわけがなかった、あの子も一氏のことが好きで、私も一氏のことが好きで、だからこんなことになったなんて。
そんなことを言ったら、なんだかんだで一氏はやさしいから、自分のせいだと思ってしまう。
「一氏、ごめんな。」
「何が、」
「シュシュ、なくしてしもうた、せっかく一氏が作ってくれたのに…」
「……そんなん今はどうでもええやろ」
「どうでもよくない!!」
「?」
はじめて、名前を呼ばれた。それが嬉しいのか、悲しいのか、わからなかったけど、絞り出した声は想像以上に震えていた。
「どうでも、よくないよ…」
雨は勢いを増して、遠くが見えないほどになっていた。一氏は立ちあがり、私の手を握り、強く引き背中に手を回した。
抱き合うような格好になり、思わず「離して!」と言うと、少し緩んだがすぐにもっと腕の力が強くなった。
鼻の奥がつんとするのをぐっとこらえた。

金色小春は焦っていた。相方である一氏ユウジとその彼女であるがなかなか教室に現れない。
いつもそこで会うのが日課だから…というのもあるが、今日は特別、そこに来てくれとユウジからメールがきた。大事な話があるんや、と。
同じ部活の忍足謙也に聞くと、彼は学校から帰るユウジとを見かけたらしい。ユウジが自らした約束を忘れるはずがないだろうから、恐らくに何かあったのだろう。
心配で居ても立っても居られなくなり立ちあがったところで、ガラリと教室の扉が空き、息を切らせながらユウジが入ってきた。
「聞いたで、ユウくん。ちゃん大丈夫やった?」
「大丈夫やけど…大丈夫やない…。っていうか、小春知ってるんか?…誰やあんなこと噂しとるの。」
「あんなことって何?」
「は?」
どうやらかなり話が食い違っているようだ。とりあえず、ユウジを落ちつかせて、椅子に座らせ、話を聞くと、どうやらは大変な事件に巻き込まれたいたようだ。
それで、ボロボロになった彼女をいったん家に送り届けて、ユウジは再び学校に戻ってきたのだという。
「何も言わへんかったんけど、何かあったんやろな、って言うのは聞かんでも分かった。」
「…うん。」
「……でも、あいつ、泣いてへんかったな。」
ユウジは下を向き、ぽつりとつぶやく。
小春にはなんとなく、思い当たる理由があった。かといって、ユウジを責めることもできないし、かと言って褒めることもできない。ただ、取り返しのつかないことになってしまった。
言葉を選び、小春が何も言えずにいると、ユウジは顔をゆっくり上げて、真っ直ぐと小春の顔を見た。
「それでな、小春、頼みがあるんやけど…。」
「……なんやねん、」
ユウジは頭を下げつつも、珍しく饒舌だった。こんな事件があったと教師や生徒会が知ったら何か処分があるのかもしれないが、生徒会役員である小春の権限で明日のグランプリ予選は中止にしないでほしいということ。なんとしてでもにも明日のステージを見せたいのだということ。
そして、のため、自分のため、明日のステージで披露するネタを変えたいということ。
「アイツが泣かへんから、泣き笑いさせたろって思てん。」
「……前日でネタ変えるって…ほとんど練習もしてへんのに、どういうことか分かってるん?」
小春の言葉にユウジは強く頷く。思わず頭を抱え、ため息をつき、そして、相方の顔をまっすぐ見た。
「本気なんやね。」
「もちろん。」
「今夜は徹夜やで。」
「分かってる。」
「衣装は?」
「さっき少し手直しした。」
「そう…。」
少し沈黙が訪れる。ちらりと窓の外を見ると、先ほどまで土砂ぶりだった雨はすっかりあがっていて、遠くの方に虹が見える。小春は立ち上がり、小さく深呼吸した。
「やるで、一氏。覚悟はええか?」
「当然や、小春。任せとき。」

朝起きたら、一氏からメールが届いていた。昨日の夜に送ってくれたのだろう、『明日のステージ、絶対見に来い。』と書いてある。
昨日の今日だ。なんか一氏に会うのは気まずいし、たぶん例の女の子達も見に来ているだろうし。それに、頬がまだ少しじんじんするから、きっと腫れが引いていない。こんな顔、誰にも見せたくない。
「いきたくないな。」
と、ぽつりとつぶやくと、急に携帯の着信が鳴った。ディスプレイには『一氏ユウジ』と表示されている。
先ほどの考えが読まれてしまったのだろうか。おそるおそる、通話ボタンを押して電話を耳にあてた。
「も、もしもし…?」
「お前、今どこや」
「え、い、家…だけど…」
「なんでやねん!来いっていうたやろ!」
「でも!だって!メールさっき見て!」
「ええから来い!来おへんかったら殴る!」
「わかった!行く!行くから!すぐに!!」
慌ててそういうと一氏は「絶対やからな」と念を押すように言って電話を切った。
そんなにも、私に今日のステージを見せたいのだろうか。
大きく伸びをして、ベッドから抜け出す。そこまで言うなら、見に行ってやろうじゃないか。
その前に、酷く腫れているこの頬に湿布を貼りたい。

会場である四天宝寺華月はすでに人でいっぱいで、私は遠慮しながら一番後ろの席に腰かけた。頬の湿布がきになるが、たぶんみんなステージの方を見ているから、私の顔なんか見ていない。
座ったらすぐに二人の出番で、大歓声の中挨拶する2人を見て、拍手をしながら少し誇らしい気持ちになる。息をつく間もなく、一氏が口を開く。
「じつは先日彼女ができましてん」
「なんやねん一氏、惚気か。」
「いや、小春のことも今まで通り好きやで!」
「そういうこと聞いてるんやないねん!」
「でもなあ、そいつ小春と違って筋肉無いから、妙な奴に手え出されへんか心配で心配で…。」
「私かて好きでこんな筋肉つけとるわけやあらへんわ。」
「それでな、俺はそいつらに言ってやるつもりなんや。『俺の女に手を出すな!』って…」
「あかんあかん、そんなんじゃあかんやん。すごみもなんもあらへんやん。もっとヤクザのように怖く言えへんの?」
「『俺のぉ、女にぃ、手を出すなぁ!』」
「アナゴさんやあらへんのやから変なタメ入れんで!」
「『俺の女に手を出すなバカヤロ!』」
「あー、ビートたけしさんな。本人がやったらえらいすんませんってなるんやけど、あんたがやっても全然怖くならへんねん。」
何度か私に見せてくれたネタと全然違う。いつもの小春ちゃんがボケて一氏が突っこむというスタイルとは全く逆のパターン。一氏が様々な人物のものまねをしながらひたすら「俺の女に手を出すな!」と言っていき、小春ちゃんが面白おかしく突っこみを入れていくというスタイルだ。
小春ちゃんが突っこむ度にどっかんどっかん笑いが起きる。おそらくこのネタは、昨日の夜に急遽作りなおして仕上げたものなのだろう。それはきっと。自惚れでなければ、私のため。
こんなすごいことができる、これが、この二人の力なんだ、と、鳥肌が立った。
客席の中ほどに座っていた数人の女の子が立ちあがって、申し訳なさそうに会場の後ろにある扉から出て行った。顔はよく見えなかったけど、きっと昨日のあの子たちだ。それでも、二人の漫才はおもろく、楽しく、続いて行く。
そして最後に、一氏が、外まで響き渡るほどの声で叫ぶ。
「お前らにもよく言うとくで!『俺の女に手を出すな!』」
「はいはい、惚気、ごちそうさん。」
「「どうも、ありがとうございました!」」
不覚にも、笑いながら顔を覆って泣いてしまった。

昨日の雨が嘘みたいに晴れて、鮮やかなオレンジ色をした夕焼けがいつもの教室を染め上げていた。
イベントの後、生徒会の仕事がまだ残っているのだという小春ちゃんを待つ間、一氏と二人、黙って遠くへ沈んで行く太陽を見ていた。
「一氏、おおきに。」
隣にいる一氏にぽつりとお礼を言うと、「……べつになにも。」とぶっきらぼうに返された。「うん、でも、おおきに。」と重ねてお礼を言うと、彼は何も言わなくなる。
「あ、せや、これ。」
ふと思い出したように一氏はがさがさとポケットを漁り、くしゃくしゃになった緑色の何かを取り出した。
「……これ…、なんで…、」
間違いない、あのとき窓から落ちて行った、一氏が作ってくれた、あのシュシュだ。夕日に照らされて、少し幻想的な色合いになっている。更にじんわりと視界がぼやけて、この世で一番綺麗なもののように見える。
「何で泣いてんねん、アホ。」
「ごめん、でも、今日は無理。蛇口しまんない…。」
「次、無くしたらタダじゃすまんからな。」
「うん、」
受け取った緑色を、もう二度と離さないように、ぎゅっと握りしめた。
次の日、校門の前で一氏と偶然会って、いつも通りぎこちなくあいさつした後は、「いくで」と私の手を引き迷いなく小春ちゃんの元へ。そうしていつも通り、小春ちゃんと話し始めた。それでもやっぱり手だけはちゃんと私の手とつながったままで、それがなんだか嬉しくて、自然と笑顔になってしまう。
小春ちゃんと楽しそうに話す一氏を見ると、彼が最近あまりつけていなかったトレードマークのバンダナをつけていることに気付いた。そして、その鮮やかな緑色に見覚えがありハッとする。
「なあ一氏、」
「なんや、」
「もしかして、このシュシュって、一氏が今つけてるバンダナと…」
言いきる前に、答えが出ていた。一氏はバッと目をそらしそっぽを向き耳まで真っ赤にさせて、小春ちゃんはクスクス笑って一氏の背中をばしばしと叩いている。
ああ、なんだかすごく幸せな気分だ。
ポニーテールの根元についたそれが、なんだかすごく誇らしくなって、少しだけ高く結び直した。