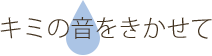子供のころにカーステレオで聞いた曲が、その人のその後の人生で聞く音楽に多大なる影響を与えるのだという。
そして、その時に聞いた音楽は、ふとした拍子に記憶の海の奥底からぷかりと浮上してくる。
浮かび上がってきた音楽は例え明確な歌詞や曲名がわからなくても、頭の中をぐるぐると回り続ける。
そんな、頭の中で鳴りつづける音と共に菊丸英二は今日一日を過ごしていた。

曖昧な記憶を頼りに、鼻歌を歌う。これであっているのかは全く分からないけれど、それでいいのだ。
曇り空を見上げて、目を閉じる。曲の続きを思い出そうとするが、思い出せない。
そのとき、ぐるぐる回り続けている曲と、全く同じメロディーがどこからか聞こえてきた。
誰かの鼻歌だろうか。それは高く、低く、秋の空気を切り裂いて、菊丸の元までやってきて、そして消える。
その音が鳴る方に足が向いたのは、ごく自然なことだった。

かすかなメロディーを頼りに、菊丸は音の主を探す。少し雨が降り始めた。
意外にもすぐに、音源は見つかった。校舎裏のベンチにこしかけて、その女の子はうたっていた。
菊丸は驚いた。彼女は菊丸がいつも顔を合わせている相手だったからだ。その女の子の名前はは。教室で菊丸の後ろの席に座っている。
「菊丸、くん?」
「あっ、ごめん」
何も言わずに、彼女のことをずっと見つめてしまっていた。
顔の前で手を合わせると、彼女は気にしていないとでもいうように手を左右に振り、首をかしげ「どうしたの?」と聞いてきた。
「あのさ、歌が、」
「歌?」
「さっきのうた、何て言うの?」
教えて、と彼女の手を掴む。彼女はぱっと目をそらし、俯きながら、消えてしまいそうなほど小さな声で、その曲の名前であろう単語を呟いた。
「恋人と分かれた女の子の歌だよ。」
「へえ……、」
菊丸が感嘆の声を漏らすとは小声で歌の続きを歌う。
優しい歌だと思っていたけれど、悲しく切ない歌だ。静かな声で歌う目の前の女の子は綺麗だけれど、彼女にはその歌のような気持ちになってほしくないと思った。
雨はやんで、空には虹がかかっていた。