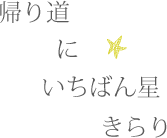学校からの帰り道でふと耳した歌に「手を繋いで並んで駅まで帰る」とかいうフレーズがあった。
確かに素敵な歌だったけれど、手を繋いで歩く相手がいない自分のことを考えると少し虚しくなる。
並んで歩きたい相手ならいるのにな。日頃の行いのせいだろうか、神様はなかなか私に向かって微笑んではくれない。

ぼんやりとそんなことを考えていたら、「あれ、ちゃん?」と聞き覚えのある声で名前を呼ばれた。
「え、滝先輩?」
「やっぱりちゃんだ、久しぶりだね。」
「はい、お久しぶりです。」
自転車に乗ってそこに居たのは、滝萩之介さん。行きの電車がたまに一緒になっていた先輩だ。…そして、彼こそが、私が並んで駅まで歩きたい相手。
部活が違うから、帰り道に偶然会うなんてことは稀で、駅まで一緒に帰ったこともほとんど…というか、一度もない。
滝先輩が部活を引退してしまってからは、先輩の朝練もなくなったため、行きも同じ電車に乗れずにいたから、まさかここで会えるとは思わなくて少し驚いてしまった。
「今、帰るところ?部活お疲れ様。」
「あ、はい。…先輩も部活、ですか?」
「そう、会計の引き継ぎがあってね、」
「いつもは電車…ですよね?」
「うん、でも今日は涼しくて天気もよかったから…自転車で来ちゃったんだ。」
久しぶりの先輩の笑顔に心が洗われる。一人でこっそり有難がっていると、不意に先輩が「そうだ、」とつぶやいた。
「せっかく会ったんだし、駅まで送るよ。」
「え、いいんですか?先輩、自転車なのに…。」
「気にしないでいいよ。もうすぐ日が落ちるから、女の子を一人で歩かせるわけにはいかないし、ね。」
先輩はそう言ってにっこり笑って首を傾げる。さらさらと重力に従って落ちていく髪がすごく綺麗だ。
「じゃあ、行こうか、ちゃん。」
「は、はい!」
自転車を押して歩き出した先輩に、慌てて返事をして横に並ぶ。
手は繋いでないけど…というか、私たちは別にお付き合いしているわけではなく、私が一方的に先輩のことを慕っているだけだから、手なんか繋げるわけがないんだけれど、それでも、歌のように、先輩と同じ道を歩けることがすごくすごく幸せ。あぁ、神様ありがとう!
今なら私、しんでもいいかも。

幸せな時間というものは、とても早くすぎるものでいつのまにか駅に到着してしまっていた。
「先輩、送ってくださりありがとうございます。」
頭を下げると滝先輩は「こちらこそ、ありがとう。俺も楽しかったよ。」と笑う。
そんな先輩を見ていたら、ふとあることを思いつき、私は「あの!」と声を上げた。
「先輩、5分…いや、3分待ってもらってもいいですか?」
「え、うん。わかった。」
先輩が頷くのを確認して、私は自動販売機に走る。小銭を入れ、ボタンを押し、商品を片手に先輩の元へ急いで戻り、息を切らしながらそれを差し出した。
「コーヒー、帰り道、寒いから、カイロ代わりにしてください!」
「え、俺に?」
「はい!あの、もし、缶コーヒー嫌いだったら、捨ててしまっても大丈夫なんで!」
「…嫌いじゃないし、捨てたりしないよ。ありがとう。」
でも普通は俺が奢るところだよね、と先輩は苦笑いしながらも缶コーヒーを受け取ってくれた。
「じゃあ、俺も何かお礼をしないと、」
「そんな!気にしないでください!」
「後輩に奢られっぱなしなのは先輩のプライドが許さないんだよ。…そうだ、ちゃん。手、かして。」
言われた通りに手を差し出すと、先輩はその手のひらの上にマニキュアの容器程の大きさの小瓶を優しく乗せてくれた。中には小さくて丸い、星のような形をした物がたくさん入っている。
「これは…」
「金平糖。ちゃんにあげるよ。」
「えっ、もらっていいんですか?」
「もちろん。」
「あ、ありがとうございます!
頷く先輩に慌ててお礼を言い、受けとった瓶をまじまじと見つめた。カラフルな砂糖菓子たちが夕焼けの光を反射して、きらきら光っている。
「綺麗だよね、その瓶。」
瓶をじっと見ていたら、先輩にそう言われた。
先輩の方がもっとずっと綺麗だなんて、言えなかった。

星の形をした砂糖菓子を口の中で転がしながら、私は電車が来るのを駅のホームで待つ。
線路の向こう側の大通りの横断歩道を、先輩が渡っているのが見えた。ちょっと振り返って手を振ってくれた先輩を見て、なんだか秋らしくなってきた風の冷たさも気にならないくらいあったかい気持ちになった。