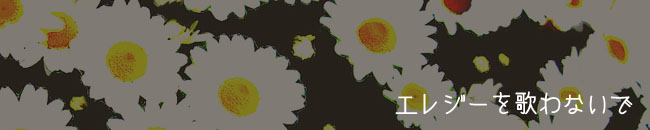プロテニスプレイヤー手塚国光が引退するらしい、というニュースは瞬く間に国内を駆け巡った。どうやら、中学の頃からだましだまし使ってきた左腕の限界がついに訪れてしまったらしい。
このことを聞いたときに、私の頭に一番最初に浮かんだのは手塚国光本人の顔ではなく、この知らせに一番衝撃を受けているであろう1つ年下のひとりの後輩の顔だった。
彼の顔を思い浮かべた瞬間、私はあと先のことを考えずタクシーに飛び乗っていた。
彼・越前リョーマにとって、手塚国光はどれほど大きな存在だったのか、私に知る由もない。だが、越前リョーマが…リョーマくんが、今まで手塚部長に一度も勝てていない、ということは知っていた。
リョーマくんは今、どんな気持ちなんだろう。
彼が日本に居るときの住居にしているマンションの前でタクシーを降りる。
海外に居るという話は聞いていないから恐らくここに居るだろう。インターホンを押す手が少し震えた。
「はい」とスピーカー越しに聞こえた声はやけに冷静だ。
「リョーマくん!私だよ!だよ!」
「え、さん?」
なんで…とか、どうして…とか小さな声で言っているのが聞こえたけど知ったこっちゃない。何も言わずにいると、「…とりあえずあがってください。」と声が聞こえ、同時にマンションのオートロックが解除された。
そのまま奥に進むと中学の頃と比べたら随分と背が伸びたリョーマくんがそこに居て、立ったまま
ぼんやりとテレビを眺めていた。流れているのは、手塚部長引退のニュース映像だ。
「リョーマくん、」
声をかけるとリョーマくんはこちらを振り向いて私の方に近づいてきた。
「何で来たの、」
「その……、手塚部長の話聞いて…、リョーマくんが…、心配で…」
「…別に、心配するほどのことじゃないし。さん昔から俺のこと気にしすぎ。俺、そんなにメンタル弱くないし。」
「でもっ」
反論しようとする私に、だいじょうぶ、と呟いて彼はそっとわたしを抱きしめた。普段そんなことをするような人ではないのに。
私を抱きしめるその手は小さく震えている。……ほんとうは、大丈夫なんかじゃないくせに。
密着している彼をぐっと押して自分の体から離す。そしてそのまま驚いた顔をしている彼の唇に強引に口付けてやった。
「だいじょうぶ。」