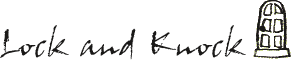「あ、」
テスト前の休み時間、私はペンケースの中を見て思わず声を出してしまった。我らが3年2組はなんだかんだ言って真面目な子が多いから、こういう時間はほぼ全員席について教科書を見なおしたり、問題集の問題をもう一度解いてみたりと、テスト勉強に余念がない。そんな中だったから、意外と私の声は響いてしまって、周りの注目を集めてしまった。小さくジェスチャーで周りの席の人たちに詫びを入れてから、もう一度自分の手の中の小振りな入れ物を見つめ、溜息をつく。
消しゴムを、忘れてしまった。これではテストどころではない。鞄をひっくり返しても、見つからない。自分の顔がみるみる青く染まっていくのが鏡を見なくてもわかる。
「さん、」
途方に暮れているところで、不意に小声で名前を呼ばれた。勢いよく声のした方を向くと、隣の席の大石くんが心配そうにこちらを見てきていた。
「どうしたんだい、さん。体調でも悪いの?」
「あ、その……」
小さい声だけど真面目な表情で聞いてくる大石くんに、まさか『消しゴムを忘れたんです』なんて言えるわけなくて、それでも『何でもない』とも言えなくて、思わず下を向いてしまう。
「もしかして……何か忘れものした?」
「え?」
大石くんはエスパーなんだろうか。驚いた私を見て「やっぱり」と笑った。
「教科書…じゃないな。ノートも机にあるし……もしかして、消しゴム?」
少し頷くと大石くんは「ちょっとまってて」と言って彼の机の上の銀の缶ペンケースから、白い消しゴムとカッターナイフを取り出した。そして、あろうことかその消しゴムを真っ二つにしてしまった。そして、半分になった消しゴムの片方を「はい」と私に差し出してくる。
「これで、大丈夫。安心していいよ。」
「え、でも、大石くんの消しゴム…」
「困った時はお互い様だろ?」
「だけど……」
「俺がこうしてあげたいって思ったんだから、さんは気にしなくていいんだよ。」
そう言って大石くんはまた笑う。そうしてその笑顔のまま「困った時はいつでも力になるから」なんて言うんだから、さっきまで青かった私の顔が一気に熱くなるのも必然といえるだろう。
「ありがとう、」と小声で言うと大石くんはやさしく「どういたしまして」と言ってくれた。