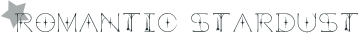何がメリークリスマスだ。企業の戦略に踊らされているバカな日本人共め。日本人なら日本人らしく、おごそかに年末を迎えるべきじゃないのか?
そう日吉が吐き捨てるように呟くと、何故か目の前の席に座ってこちらを向いていたが大まじめな顔で頷いた。
「日吉くんの言うことはもっともだと思いますよ。私もクリスマスは爆発すればいいと思っている。」
「……別にお前に同意は求めていないけどな。」
顔を見ずに、窓の外の雪を眺めながらそう返すと彼女は「つれないなぁ、日吉くんは。」と頬を膨らませた。「うるさい」と手刀をきめてやろうとしたら、見事にかわされた。イライラして溜息を吐く日吉を無視して、彼女は「でも、」と続けた。
「それでも、そんな風に思っていたら、楽しいことも楽しくなくなっちゃうと思いませんか?」
「どういう意味だ?」
「クリスマスって本来は楽しい行事なんだから、どうせだから思いっきりはしゃいじゃおうってことですよ。バカな日本人に成り下がってもいいじゃないですか、今日くらいは。」
今日くらいは下剋上もお休みしていいんじゃないですか?そう言って彼女は悪戯っぽく笑った。

振り払おうと思えば振り払うこともできた。断りたかったら断っても良かった。でも、目の前に居る彼女にされるがままになっているのは、コイツはなにか面白いことをしでかしてくれる、というぼんやりしているけど確かな信頼のようなものがあるからだ。本人に面と向かっては絶対に言わないけれど。
そんなことを考えていたら、どんどん学校から離れて、人影の少ない住宅街までたどり着いていた。「コンビニに行くんじゃなかったのか?」と聞いたら「まぁ、それはあとでいいですよ」と返される。
「あとって、なんの後だよ……」
「…まぁ見ててくださいよ。」
そうが言った途端に、辺りがパッと明るくなった。目を丸くする日吉を見てがくすくすと笑う。
「この時間になると、この辺りのイルミネーションが一斉に点灯されるんです。今日は雪も降っているから、一段ときれいじゃないですか?」
の話半分に聞きながら、日吉は眼前の光景を瞬きせずに眺めていた。赤・緑・青・橙、色とりどりの光がそこには溢れていた。「すごいな」と思わず声に出して言うと、は「でしょう?」と自分がやったことでもないのに自慢げに笑った。そんな彼女を見たら少しイラっとしたから、思いっきり頭をど突いてやった。
でもまぁ、これならクリスマスも悪くないかもしれないな。不思議といつもよりも気分が上を向いているような気がする。思わずふっと笑い声が漏れた。
「あれ?日吉くん、笑ってるんですか?」と聞かれてもう一回彼女の頭を叩いてやったのは言うまでもない。