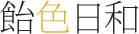思わず閉じてしまっていた目を恐る恐る開くと、段ボールの代わりに俺が受け止めていたのは、同じクラスで新聞部のだった。その自分より低い位置にある頭をしばらく眺めていると、はハッとしたような顔をして俺の顔を見て、それから慌てたように俺から離れ、尻もちをついた。
「ひ、日吉くん!ごめんなさい!」
「……別に。」
挙動不審にきょろきょろするに「怪我は?」と聞くと首を横に振ったため、とりあえずホッとする。そして「どうしてあんなに急いでたんだよ」と聞くと彼女は「えっと、」と言葉を濁らせた。
「昔の新聞を参考にして原稿書こうと思って……それで高い所にある資料取ろうとしたら棚にあったものも一緒に全部落ちてきちゃって……普通に全部直すのは大変だからって思って脚立を借りに行こうと思ってたんだけど……」
「そこで俺とぶつかったわけか、」
倉庫の中を見ると、棚の一つの中身がほとんどすべて床に落ちてしまっていた。思わず溜息をつくとはびくんとかたを震わせて、涙目でこちらを見た。あぁ、ちがう、そんな顔をさせたかったんじゃないんだ。それでも「ご、ごめんなさい!」と頭を下げる彼女に「何でまた謝るんだよ、」と無愛想な返答をすることしかできなかった。「だって、」と俯く彼女の瞳にできた泉は今にも地面に水を落としてしまいそうだ。
どちらにしろ、ここを片付けてしまわなければ話にならない。未だ座り込んだままのに「ほら、」と手を差し伸べると彼女は不思議そうな顔をしながらも俺の手をとる。そのままその手を引っ張り立ちあがらせると、やはり彼女の頭は俺よりもかなり低い位置にあった。
「こっちは俺がやっておくから、そっちの方を整理してろ」
床に散らばった古新聞と写真を順番にを示しながら俺がそう言うと、は「う、うん!」とどもりながらもしっかりと頷いた。
腰をかがめて作業にかかろうとする俺にが声をかけてくる。
「あの、日吉くん!」
「なんだよ」
「ありがとう」
そう言ってははにかむように笑った。「……別に」と再び無愛想にしか返せなかった俺の顔が熱くなってることに彼女が気付かなければいい。