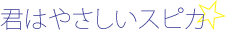「欲しがればなんでも手に入れられるような気がしていたんだ」
「まぁ、貴方ならば何でも手に入るでしょうね」
「…本当はそんなことはないんだけどね。」
そう言って彼はくすくすと笑ってから「でも」と続ける。
「そうやって、何でも手に入ると思っていたときにも、僕の手に入らなかったものが二つだけあった。」
彼がたてた2本の指をまじまじと見つめながら私は「……それって、何?」と問う。すると、彼は「ひとつは、星。」と今頭上にあるキラキラ瞬く光の数々を示した。
「もう一つは?」
「もう一つは……君だよ。」
そう言って彼は微笑んで私の頬をなでる。胸が激しく鼓動を打つ。心臓がいまにも口から飛び出しそうだ。もしも本当にそうなってしまったら、私の血液を体中にいきわたらせるその臓器は彼に攫われてしまうんだろうか。いや、それ以前に私の心はもうすでに、彼の世界に飲み込まれて、彼に攫われているのかもしれない。
「ねぇ、不二、」と名前を呼ぶと彼は「なんだい」と優しく答える。彼が望むのなら何だってしてあげたいと思えた。それが彼に攫われいるということになるのなら、私は甘んじてそれを受け入れよう。そんなことを考えてしまう辺り、私も大概彼に毒されている。
「そんなに欲しいのなら、私が星を取ってきてあげようか?」
私がそう言うと彼は少し驚いたような顔をしてから「じゃあ、お願いしようかな」と微笑んだ。
そうして私は夜空に手を伸ばして、星を掴もうとする。空気が乾燥しているからか、それは驚くほど近く、今にも落ちてきそうに思えた。
指先が何かとがったものに触れて、チクリと痛んだ。それは星だったのかもしれないし、そうではなかったのかもしれない。みるみるうちに、私の指先には真っ赤な滴ができあがる。不二は自然な動作で私の手を取って、その指を口に含み「甘いね」と呟く。「そんなわけないでしょう」と言う私を無視して彼は「星を食べたときの味みたいだ」と笑う。
「食べたことあるの?」
「ないよ。でも、こういう味がするんじゃないかと思ってる」