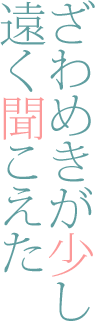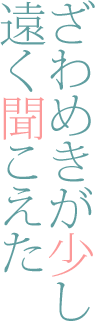夏休みが終わる。蝉は煩く鳴くのを止め、夜になると鈴虫の声が聞こえるような季節になってきていた。真っ赤な夕焼けが差し込む部室でマネージャーである彼女はふわふわに洗濯されたタオルを畳んでいく。その横で、日吉若は酷く真剣そうな顔をして腰かけていた。
「お祭り?」
首をかしげてそう聞く彼女に、日吉は「はい」と頷く。
「俺の家の近所で、毎年8月の最後にやっているんです。小さいものなんですけど……、」
「そうね、日吉が綿菓子を奢ってくれるのなら行くわ。」
日吉がすべてを言いきる前に、彼女はそう答えた。「よりにもよって綿菓子ですか」と溜息をつくと「駄目?おいしいのよ?綿菓子。」と子供が縋るような目をするからまるで自分が悪いことをしているみたいだと錯覚してしまう。
「駄目とはだれも言っていないでしょう。綿菓子くらいおごってあげますよ。」
「本当?ありがとう、日吉」
とたんに彼女は表情を変えて、にっこりと笑った。そのことにほっとして、無意識のうちに強張っていた全身の力が抜ける。そんな彼を余所に彼女はちょうど部室に入ってきた忍足と向日に「ねぇ聞いて、私、日吉とお祭りに行くの。綿菓子を奢ってもらうのよ。」とか報告している。すぐに2人からからかいの声が飛んでくることを予想して、日吉は一度緩んだはずの頬の筋肉がひきつっていくのを感じた。
それから「何着ていくんだよ」とか「もうすぐやな、気張りや」とか言ってくる先輩達にいらいらしているうちに時は流れ、今日はもうそのお祭りの日だ。西の空にはまた真っ赤な夕日が沈みかけている。待ち合わせ場所の駅前に早く来すぎた日吉は、駅に備え付けられている時計と、自分の携帯電話を交互に何度も確認する。落ち着け、と自分に何度も言い聞かせてはいるものの、この状況で冷静でいろという方が無理な話だった。
しばらくして、「日吉」と名前を呼ばれ振り返ると、「お待たせ」と微笑んだ彼女は涼やかな花浅葱色の着物を着た彼女はあまり履き慣れていないのであろう下駄をカラカラと鳴らして近づいてきていた。いつもは下ろされている長い髪も、今日は高いところで一つにまとめられている。気軽に『素敵だ』とか『綺麗だ』とか『可愛い』とかの言葉を舌に乗せることができない自分の不器用さを呪った。代わり、というわけではないが彼女の手をとり軽く握る。はぐないようにこうするんだ、と自分に言い訳をして。「日吉ってば大胆」とかいう彼女の驚いたような声は聞こえなかったふりをした。
金魚すくいでも、ヨーヨー釣りでも、射的でも、彼女には敵わなかった。ここは普通、男の方ががんばるところだろう。あまりにも華麗に何でもこなす彼女を見て、日吉は泣きボクロが特徴的なテニス部部長を思い出し、それを振り払うように首を左右に振った。どうしてこんなところまで来て跡部さんのことを思い出さなければならないんだ。そんな日吉には目もくれず、彼女は先ほど彼が奢った綿菓子を嬉しそうに頬張っている。「幸せそうでいいですね」と呟くと彼女は二・三度瞬きして「ねぇ、日吉知ってる?」と真剣な表情をして彼の目を見た。
「何をですか、」
「夏の終わりのこういう場所には、幽霊が出るらしいわよ。」
あまりにも突拍子の無い発言に思わず「はぁ?」と声を上げてしまった。それが意に介さなかったらしく、彼女は少し首をかしげる。
「あら、日吉はこういう話題が好きなのだと思っていたけど、そうではないの?」
日吉がつまらなさそうだったから言ってみたのに、と唇を尖らす彼女に貴女のせいですなんて言えるわけがなくて、日吉は深々と溜息をついた。
「まぁ、嫌いではないですけど」
「けど?」
今は貴女がそばに居るから、幽霊なんかどうでもいいんだ。とはやっぱり口に出せなくて、遠くで花火が打ち上がる音に合わせて「なんでもないです」と呟いて誤魔化した。
♪夏祭り(Whiteberry )