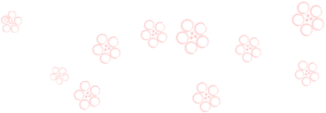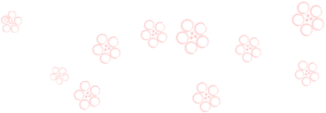彼の手が私の頭を、手を、足を、撫でる。その手はとても冷たかったけれど、彼に触れられたところはどんどん熱くなっていくように思えた。
「やぎゅうくん、」
名前を呼ぶと彼は、眼鏡の向こう側から真っ直ぐ私を見て「痛くはないですか?」と聞く。そう聞かれると私は、「いたくない」とゆるゆる首を左右に振ることしかできない。
どうしてこんなことになってしまったんだろう、と思い返す。そう、それは3時間目の前の休み時間、科学室に移動している最中だった。
いつも通り、友達と話しながら階段を上っていると、不意にずるりと階段から私のつま先がすべり落ちた。そしてそのまま、私の体もふわりと浮いて落ちていく。最後に聞いたのは「さん!」という柳生くんの声だった。友達や周りに居た人も何か言っていたのかもしれないけれど、普段は落ち着いている彼の大きな声が珍しかったからか、他には何も聞こえなかった。
そして、気づいたら私は保健室のベッドにいた。
目が覚めて、まず目に入ったのはベッドの横にある椅子に腰かけた心配そうな柳生くんの顔だった。「大丈夫ですか?」という問いに、ぼんやりしている頭で頷くと、彼はほっ、と溜息をついた。
「ですが、貴女が気付いていないだけでどこか怪我をしているかもしれません。失礼とは思いますが、調べさせて頂けますか?」
私は再び、ぼんやりと頷いた。それがまさかこんなことになるなんて、夢にも思わずに。
「も、もういいよ、大丈夫だよ、柳生くん。痛くないし、柳生くんが居てくれたから大したことなかったし……」
「あとから痛くなるかもしれないでしょう?こういうときは気が動転して感覚が麻痺していることもありますから」
するり、と柳生くんの指が私の指先に触れた。ゆっくりと慈しむように撫でられて、指先だけでなく体全体がじわじわと熱を持つ。その熱は顔にも集まってきて、私の頬は赤く染まる。思わず俯くと、柳生くんの手は私の指から離れて顎の先移動した。そうしてくいと持ちあげられて、正面を向かされる。
「さん、」
「な、なに?」
「私の事、お嫌いですか?」
そう言って柳生くんはまた真っ直ぐと私を見る。そしたらやっぱり私は、「きらいじゃない」とゆるゆる首を左右に振ることしかできないのだ。
「ならよかった」と微笑む彼を見て、もしかしたら私
は彼のことを