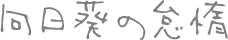「そんなことを言われても、わたしははじめくんとは違ってこの山形しか知らないんだから仕方ないじゃない。」
「だからあのときに言ったじゃないですか『僕と一緒に来ませんか』って。」
「なにそれ、言われた覚えないんだけど」
「……そうでしたっけ?」
「頭で考えてはいたけれど口には出していなかったのかもしれませんね」と言うと、彼は誤魔化すように私の隣で横になった。そんな彼を見て、私は驚くことしかできない。どうしたんだろう、今日の彼はやけに素直だ。あつさのせいだろうか。目を瞬かせていると、彼はごろりと寝がえりを打って私の方を向き「どうしたんですか?」と怪訝そうな顔をする。それが、いつもはきちんとしている彼の姿とはあまりにもかけ離れていて、少し笑ってしまった。そして、彼がこんな姿を見せるのは家族以外では私の前だけなんじゃないかと考えて、ちょっとだけ優越感に浸り、また笑う。「何を笑っているんですか、」と額を小突かれても、緩む口元を押さえることはできなかった。
やっと笑いが収まり彼の顔を見ると、そのハシバミ色とかっちり視線が重なった。その瞳が、嬉しさと、懐かしさと、寂しさが綯交ぜになったような色をしていたから、私は思わず「はじめくん、私が居なくて寂しい?」と聞いてしまった。それはとてもとても小さな声だったけれど、どんなに小さな声で喋ってもそれをとらえてくれるのがはじめくんで、だから私ははじめくんが好きだった。
今度は彼が目を瞬かせる番だった。そして、再び私の方を見て「んー、そうですねぇ、」と寝ころんだまま口元に手を当てた。
うーん、と唸りながら、彼は口にあてている方とは反対の手の指を私の髪の毛に絡める。彼が長いほうが好きですと言った時からのばし始めたその髪はさらさらと細い指に絡まっていく。
「寂しくないことはないですよ」
「え……本当に?」
「こんなところで嘘をついてどうするんですか」
はらり、と私の髪の毛が縁側の床に落ちた。そうして髪の毛から離れた手は私の頭を軽く叩く。「本当に馬鹿ですね」という言葉と共に。
「でも、は来なくて正解だったかもしれませんね。」
「どうして?」
「みたいにぼんやりしていたら東京では何に巻き込まれるか分かったもんじゃありません。」
「バカにしているの?」
「していませんよ。事実を述べたまでです」
楽しそうにそういう彼の笑い声に重なるように風鈴がチリンと鳴る。その髪の毛に、今度は私の指を絡めてみた。彼はそれを拒絶することなく、ゆっくりと目を閉じる。再びそれが開くまで、あつい夏はもう少しだけ続く。