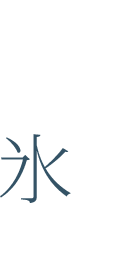そんな彼と隣の席になったのは、三年生が始まってすぐの席替えのときだった。
これからよろしくね、と挨拶をすると、中学生らしくない低くて落ち着いた声で「よろしく」と返してくれたのをよく覚えている。
それから、真面目そうな顔をして一体何を考えているのだろう、とよく彼の横顔を覗き込むようになった。そうしていたら、八割くらいの確率で手塚くんが「どうした?」と不思議そうに聞いてくる。そういう時、私はにっこりわらって「なんでもないよ」と答えるのが常だった。
完璧で隙の無い彼と、普通で平均的な私。ちぐはぐな組み合わせだったけど、それなりに仲良くやっていたと思う。

それでも、無駄に輝く太陽はジリジリと照りつけてきて、日焼け止めを塗った肌にたらりと汗がつたう。時折吹く風は涼しいけれど、アブラゼミの煩く鳴く声はその心地よさを半減してしまいそうなくらいだった。
スーパーの自動ドアをくぐると、そこは天国だった。少し下降しはじめていた気分は再び上昇する。お店のロゴマークが描かれたピンク色のカゴを手に取り、人参を吟味してる若い奥さんの横を通りすぎた。目指すは卵コーナーと氷菓コーナーだ。おまけのカード付きのスナック菓子を片手に走り回っている小学生が目に入り、思わずほほが緩んだ。
お得さを求めるおばちゃんたちにもみくちゃにされつつ卵をゲットし、今私はアイスが大量に入った冷凍庫の前で立ち止まり、腕をくみ、考え込んでいる。兄に何のアイスが食べたいのか、聞くのを忘れてきてしまった。携帯で電話をかけて聞こうかとも思ったが、どうやら家に置いてきてしまったらしい。普段はメールも電話も滅多にしないのに、こういうときに限って忘れる自分の間抜けさを呪った。
唸りながらたくさんの種類のアイスを眺めていると、横からすっと男の人の手が伸びてきた。振り返ると、見覚えがある、だが、この場には似つかわしくない顔がそこにあり、私は思わず目を見開いた。
「え、手塚くん?」
「…か」
「やはりな」とか言いながらそこに立っていたのは、左手にガリガリくんを、右手にピンクのカゴを持った手塚国光だった。

「『どうしたの』と言われても、スーパーですることは買い物以外無いだろう。」
「…そっか、そうだよね、」
手塚くんの言っていることは当たり前なのだが、相手が彼だからかものすごく違和感を感じる。ピンクのカゴと卵とガリガリくんがこれほどまでに似合わない男は他に居ないだろう。だからこそ、『手塚くんはスーパーの安売りにだって行くしガリガリくんだって食べる』という意外なギャップを知る人はそんなに多くは無いんじゃないだろうか。こんな彼の姿を知る私は貴重な人材なのかもしれない。そう思うと思わず頬が緩んだ。
ニヤニヤしていると、目の前に居る手塚くんがいつものように「どうした?」と聞いてこちらを見てきたので「なんでもないよ」と答え、必死で表情筋をひきしめる。それでも尚、彼は怪訝そうな顔をしているので、私は慌てて「あっ、そういえば」と話を反らした。
「手塚くん、早くレジに行かないと帰る前にアイス溶けちゃうよ」
手塚くんの手にある青い袋を示しながら言うと、彼は「それもそうだな。」と頷いてから「はどうする?」と聞いてきた。
「私はもう少し何を買うか考えてから行くよ」
「…そうか」
沈黙が訪れる。彼との沈黙は嫌いではない。でも今日は、スーパーの明るい雰囲気と楽しげな音楽がこの空気にミスマッチで、なんとなく居心地が悪かった。沈黙に耐えかねて口を開こうとしたら、手塚くんの方が先に「、」と私の名前を呼んだ。
「それでは、また明日な」
「え、あ、うん。また明日ね、手塚くん。」
意外にあっさりと別れの時は訪れた。まぁ、また毎日学校で会えるのだから当然といえば当然なのだが。
立ち去っていく手塚くんの背中を見守る。やっぱり、ものすごい違和感だ。レジのお姉さんに「袋はいりません、エコバッグがあるので」とか言う彼を想像して思わず吹き出してしまった。
さて、私もそろそろ帰らなければ兄と母に文句を言われてしまうだろう。明日また会ったら彼になんて声をかけようか、なんて考えて、迷わずガリガリくんを2つピンクのカゴにいれた。