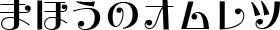「英二はいつも、オムレツつくるよね。なんで?」
ある時、私がそう聞くと、英二は目を大きく開いて二、三回ぱちぱちさせた。
「はオムレツ嫌いだった?」
「ううん、そうじゃないよ…でも、」
嫌いなわけではない。でも、不思議だった。いつも、私の心の隙間をそっと埋めるオムレツの魔法のような力が。英二がいつもそれを作るのには何か特別な理由があるのではないか、そう思ったのだ。
「ううん、別に特別な理由とかは無いんだけどなー」
「え、そうなの?」
「うん、」と頷いて英二は少し笑った。
「あえて言うなら」
「あえて、言うなら?」
「俺がオムレツ好きだからかもしれないけどさ、なんか食べたら元気が出る気がして。で、にも元気出してほしいって思った時はオムレツ作るようにしてるってわけ」
私はぎゅ、と英二の手をにぎった。言いたいことはあったけど、言葉にするのはは照れくさくて何も言えなかった。この感謝の気持ちが、手のひらの熱に混ざって伝わればいい、なんて都合のいいことを考えた。

その日は雨が降っていたのか、晴れていたのか、今はもう思い出せない。ただ一つ覚えているのは、英二がとてもつらそうな顔をしていたということ。いつもきらきらしている瞳は光を失い暗い陰を落としていた。
見よう見まねで私はオムレツを作った。うまく殻が割れなくてボウルに入り込んだり、フライパンに卵がくっついたり、床に落としてしまいそうになったりして、できた物はとてもいびつな形で「美味しそうだ」とは言い難いような代物だった。泣きそうになりながら奇妙な形に歪んだオムレツを英二に差し出す。なんだか涙が出そうだった。本当に泣きたいのは英二の方のはずなのに。
「、」
黄色いふわふわになるはずだった物体を口に入れてから、英二は小さな声で私の名前を呼んだ。
「これ、すっごく美味しーよ。ありがと」
上手く笑えてないよ、ばか。だなんて、言えなかった。せき止めていた涙が溢れて止まらない。オムレツには、感謝も、元気も、混ぜ込めることができなかった。自分がつらいときより、彼がつらいときの方が心が痛むのだということを知った時だった。

久しぶりに早起きをして、身支度を整えてから、着なれたエプロンをつけた。もう卵を割るときに殻が混じることは無くなっていたし、フライ返しを使わなくてもフライパンの中の物をひっくり返すことができるようになっていた。
「おはよ、」
いつの間にか、英二も起きてきていて、私の横で眠そうに目をこすっていた。「髪、はねてるよ」と指摘すると「もともとだからだいじょーぶ」とのんびり返された。それが妙におもしろくて私はくすくす笑う。
「英二、今日の朝ご飯はオムレツだよ」
「うん、そだね」
「私が愛情を卵と一緒に混ぜたからね。食べたら英二、私のこと好きになっちゃうかもよ」
英二は二、三回目をぱちぱちさせてからたのしそうに笑った。
「それってもともと好きな場合はどうなるのかな」
「そうだな……もっともっと私のこと好きになって、それから幸せになれるよ。私も、英二もね。」