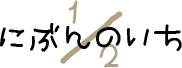「けんやくんって、かっこええなぁ」とクラスの女の子たちは言う。だが、それは間違った見解だ。彼女たちは謙也のことをなにひとつ分かっていない。あいつは、へたれだし、かっこわるいし、とにかく『かっこいい』とは縁のない存在なのだ。かっこいい忍足謙也なんて、うん、全然想像できへん。
だから、謙也の方から夏祭りに誘ってくるなんて、思ってもいなかった。なんてったって、へたれやし。真っ赤になって、どもりながら誘ってくるものだから、思わず吹き出してしまったら軽く頭をはたかれた。細胞死んでもうたらどないしてくれるん?
へたれや、とはいっても、謙也は私の好きな人やし、好きな人にかわいい姿を見せたいと思うのは女の子として当然のことやから、いつもよりずっとずっと早起きして、一人で半狂乱になりながらも浴衣を着付けて、バッチリメイクして、髪の毛もアップにして、待ち合わせの駅に来ているわけだけど、これはちょっと早く来すぎたらしい。駅前のソーラー電池で動く大きな時計は待ち合わせ時間の2時間前を指していた。いくらなんでもはしゃぎすぎやで、と自分を戒める。それでも、ニヤける口元を押さえられない。携帯を何度も開いたり閉じたりして、時間と新規着信を確認した。

知らない声。顔を上げたら1人の男が私の目の前に立ちニコニコ笑っていた。
「何の用ですか」
「キミ、一人なん?誰か待ってはるとか?」
「そうですけど……」
面倒なのにつかまってしもうた。小さくため息を漏らす。待ち合わせ時間まではまだまだ時間があるから謙也が助けてくれることは期待しないほうがいいようだ。
「でもなー、キミ、かなり前からここで待っとるよな?」
「……」
「もうその相手、来ないんとちゃう?」
あぁ、どうしてこういう奴らって、こうも回りくどいんやろうか。いいたいことがあるならはっきりいえばええのに。目の前に居る彼を無視して、携帯を開いても、目に入ってくるのはいつもの待ち受け画面。謙也はまだ出発すらしていないんだろうか。空を見上げたら、陽が西に傾いて少しオレンジ色になっていた。
「だから、な、俺と一緒に夏祭り、回らへん?」
「白石、お前、誰の許可得て人の彼女ナンパしとるんかい」
何度も聞いた声、大好きな声、めんどくさい彼の頭を軽くはたくのは、忍足謙也その人だった。
「……!謙也!」
「待たせて悪いなぁ、。」
「ううん……早く来すぎたの、私の方やし…。それより、この人、謙也の知り合いやったん?」
私が聞くと、謙也は「腐れ縁や」と言ってまた彼の頭をはたいた。
「ええか、白石、に手ぇ出したらいくらお前でもただじゃ済まんからな。」
「はいはい、わかっとる。……ほな、ちゃん、またな」
思ったよりも早く引き下がってくれた白石さんはひらりと手を振って雑踏の中に消えていった。「ええひとなんかもしれんなぁ」と呟くと「ありえへん」と返された。
「それより、」
「ん?」
「なんで、助けに来てくれたん?」
首をかしげながら、そう聞くと謙也は「あぁ」と小さくうなずいた。
「だって、は俺の彼女なんやから、おれがまもったらなあかんやろ?」
そう言って笑う謙也の顔は、いつものへたれなそれではなく、とても真剣で、くさいセリフだと分かってはいながらも少しドキッとしてしまった。
「けんやくんって、かっこええなぁ」クラスの女の子たちの言葉が脳裏をよぎった。分かっていなかったのは私の方かもしれない。謙也、今のあんたはものすごくかっこええよ。