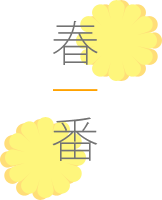突然の私のセリフに、目の前に居る彼・山本武は「は?」と間の抜けた声を上げた。それもそうだろう。いくらなんでも、話の脈略が無さすぎる。でも、このままじゃダメだとずっと思っていたのは確かなことだ。この一年間、何かあったようなきがするし、何もなかったような気もする。そんな、ふらふらした感覚のまま、この学年が終わってしまうことに私は少し焦りを感じていた。正直、しんどい。
朝や夕方はまだまだ冷え込むこの季節も、晴れた日の昼間はぽかぽかと陽が射し暖かい。そんな昼休みの屋上に、私と武は居た。暖かいとはいえ、風が強いからか、私達以外に人は居ない。そんな中、お弁当の卵焼きを箸でつまんで、尚も私は続ける。
「武はさ、部活やってるし、そうじゃなくてもツナくんたちとなんか色々楽しそうじゃん」
「そうか?」
「そうだよ。それに比べて私は何にもないんだよ。」
そう、なんにも。私の世界を構成するものは、つまらない授業とおいしいご飯とあとはちょっとのお菓子だけ。夢中になれるものが無い自分の今を一人嘆いた。
「もう私、生きてる価値なんてないかもしれないよ。死んだ方が幸せ、かも。」
そう、呟いたとたんに、武はすごく怖い顔をして黙った。お互いになにもしゃべらないまま、ただ黙々と目の前にあるお弁当を消費する。
そうして食べおわったお弁当を綺麗に片付けていたら、武が不意に立ち上がった。ゆっくりと給水タンクによってできた日陰に近寄って、そしてしゃがみこむ。そして、「なぁ、」と私の名前を呼んだ。
「なに?」
「これ、見て。」
武に近づき、屈んで彼の示した所を見ると、まだ雪が溶けずに残っていた。ところどころ汚れて灰色になってしまったそれを、そっとどかすと、あせた色の葉っぱが顔を出した。数枚の緑に囲まれて一本の茎がしっかり伸びている。その先には、まだ固い蕾。タンポポだ。
「すげえよな。日陰でさ、雪でめちゃくちゃ寒かったのに、こいつは生きてる。」
「うん…そうだね。」
「なんにもなくたって、こいつは生きてるんだよ。こいつを見ると、幸せになる人が居るんだよ。生きてるだけで、人に元気を与えるんだよ。」
「……」
「だからも、全然ダメじゃないし、生きてる価値あるんだ。」
「…うん。」
「それでも…何かしたいって思うなら、オレがその何かを見つけるの手伝うから、」
冗談で言っただけなのに、「だから、ダメだなんて、死んだ方が幸せなんて、言うなよ」だなんて、お前はどれだけいいやつなんだよ山本武。あぁ、そんな君が私は好きだ。「ありがとう」と小さく呟くと、武は笑って「どういたしまして」と言った。こんな彼がそばにいてくれて、なんだ、結構私、幸せじゃん。生きてる価値、あるじゃん。
私達はどちらともなく、目をあわせて微笑んだ。私も空に向かって伸びるタンポポのように立ち上がり、風でぱたぱたとはためくスカートを押さえて、私は深呼吸した。少しだけ甘い香りがする。冬はもうすぐ終わる。