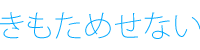さんは大人しくて、学校の中ではそう目立った存在ではなかったが、そのはかなげな表情と、透き通るような白い肌で、数多くのファンを獲得している学部内の隠れたアイドル的存在だった。僕もそんな彼女のファンの中の一人、というかなんというか、同じ日本人であったから親近感を抱いていたというのもあるけれど、とにかく、ロボットのほかに初めて興味を持った人間が彼女であったということは間違いない。
きっかけは彼女が学期末に提出して、なんとかっていう大きな機関から賞をもらっていた論文を読んだことだった。彼女は見た目に反してしっかりと主張をもっていて、更に文章を読むだけでかしこい人だということがわかった。それから、彼女の姿を自然に目で追っている自分に気付いた。こちらに来てから知り合った白さが特徴的な彼は『正チャン、それが恋だよ』とのたまったが、僕はそうは思わなかった。幽霊や、妖精と同じ、恋なんて非科学的なものは信じたくなかった。
「入江くん、」
「え?」
「入江くん、私たち、おんなじ組だよ、早く行こう。」
どうやら、考え事をしているうちに肝試しの組み分けが決まってしまったらしい。彼女のことを考えていたら、その人と同じ組になった。なんという偶然のめぐりあわせだろう。
「入江くん、もしかして怖い?」
「別に……幽霊とか信じてないし、」
「そうなの?」
「うん、基本科学で証明できないものは信じないんだ。」
同じような会話をして、姉に『嫌な奴』だと言われたことがある。だが、彼女はくすくすと笑って「入江くんって面白いんだね」と言っただけだった。その表情がいつも教室で見ていたものとは少し違って思わず面喰らってしまう。
「さんは……幽霊とか信じてるの?」
興味本位の質問だった。彼女の言葉を聞けば、自分の考え方や、物の見方が変わるかもしれない、視野が広がるかもしれない、そんな気がしていた。
「わたし?」
彼女は驚いたような顔をして、人差し指で自身を指した。「そう。」と僕が頷くと、彼女はまたくすくすと笑った。
「やっぱり入江くんって面白いね、」
「……どうしてそうなるのさ、」
困ったように眉を下げると、彼女は「ごめん、ごめん、」とほほ笑んだ。
「私はね、信じてるよ、幽霊」
「え?」
「だって、私……」
彼女の言葉の続きを聞くことはできなかった。どこかで誰かが僕の名前を呼んでいる。
「入江くん!」
「え……さん?」
僕の名前を遠くで呼んでいたのは、先ほどまでそこで会話をしていたその人だった。予想外の出来事に、体を動かすこともできず、僕は数回瞬きした。
「入江くん、どこに行ってたの?私たちおんなじ組だよ、早く行こう。」
「え、ちょっ、まって!」
「……なあに?」
彼女は首をかしげる。首を傾げたいのはこっちのほうだ。
「えっと、僕、さっきまでさんと一緒にいたと思う、んだけど……」
「え?」
今度目を瞬いたのは彼女のほうだった。そして「私はずっと、みんなと一緒にあっちのほうに居たんだけど……」と困ったような顔をする。
「じゃ、じゃあ、さっきまで僕と居たのは……」
ゆっくりと、先ほどまで彼女がいると思っていた隣を見る。そこには誰かがいた痕跡はなく、ただ、夜の闇が広がっていた。
「あ、」
彼女が声を上げる。視線の先は僕の足元、ではなく、
「これ、誰のだろう……」
僕が立っていたすぐ横に、きちんと揃えられて置いてあるピンクのコサージュがついたサンダルだった。