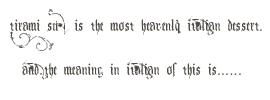「なぁ、、」
目の前にいる幼馴染の少年はいつになく真剣な顔をしている。私が「何?」と聞くと、彼は困ったように目尻を下げた。
「ごめん、小さい頃にした約束、破ることになっちまった。」
「え、どういうこと…?」
「オレ、卒業したらイタリアに行くことになった。たぶん、日本には帰ってこれないと思う。」
時が止まる。彼がおごってくれたココアがたっぷりかかったティラミスは空を切るような味しかしなかった

けたたましい目覚ましの音で目が覚めた。ずいぶん昔の夢を見ていたようだ。幼馴染である、山本武との夢。最後に会ったのが中学の卒業式だったから、もう何年会っていないことになるのだろう、と、数えようとしてやめた。そんなことをしてもむなしい気持ちになるだけだ。
「起きなきゃ、」
今日は休日だが、映画に行く約束をしている。布団と今まで見ていた夢への未練を払いのけて起き上がり、テレビのリモコンの電源ボタンを押す。どんな夢だったっけ?そうそう、最後にあいつと話した時の夢だ。笑顔が素敵なお天気おねえさんの「今日は夜から雨になるでしょう」の声を聞きながら朝食の準備をしつつぼんやりと夢の内容を思い出す。
あの夢には続きがある。「イタリアに行く」そう言った武に返す言葉がその時の私は思いつかなくて、「そう、」と一言言ったきり何も喋れなくて、大好きなはずの味のしないケーキを食べた後、家に帰って涙が枯れるまで泣いた。それが、中学三年の二月のこと。次の日から、私は武と話せなくなった。…いや、話せなくなったんじゃない、話さなくなったんだ。武は何度も私に話しかけようとしてきてくれていたし、一年のころから武と仲良くしてきた沢田や獄寺だって、私たちを気遣って、「今日は山本と一緒に帰ったら?」とか「あの野球バカ、今日は部活ないみたいだぜ」とか、背中を押すようなことを言ってくれていた。それでも、私は武のことを避け続けた。中学を卒業して、もう会えなくなったとき、思い出が多ければ多いほど辛くなる気がしたから。卒業式の日、武に見つからないように走って家まで帰ったのは今でも覚えている。
正直、今では後悔している。人生に後悔は付き物というが、あとにも先にもこれほど大きな後悔はないだろう。もっと話をしておけばよかった。もっと一緒にいればよかった。お礼を言えていないことも、謝れていないこともたくさんあった。そういえば、あのときおごってもらったティラミスのお礼もまだしていない。
考え事をしていたら、牛乳をこぼした。我に返って時計を見ると、約束の時間まであと30分。顔も洗っていないし、メイクもしていない。駅までは自転車を飛ばして20分。
「……ノーメイクで出かけろってか。」
溜息をついて、まだ半分も食べていない朝食を未練がましく片付け、家具に様々なところをぶつけながらも洗面所へ向かう。……約束と言えば、
「小さいころ武とした約束って…なんだったっけ?」
小さな私のつぶやきは蛇口をひねって流れ出した水の音にかき消された。
駅に着いたのは約束の時間の5分前だった。家を出てジャスト15分。記録更新である。急いで手櫛で乱れる髪を整えて、待ち合わせ場所の噴水に向かうと、見覚えのある後ろ姿を発見した。会社の後輩である彼は、私の所謂『恋人』というものなのかもしれない。『付き合ってください』『好きです』云々の儀式は全くしていないが、仕事帰りに飲みに行ったのをきっかけに意気投合し、それからよく一緒に出かけるようになった。それだけか、と聞かれたらまぁそれだけなのだが、社内では私と彼はそういうお付き合いをしているということになっているらしい。まぁ、別に隠すことでもないのでこうやって休日に二人で堂々と映画を見に行ったりしているわけだが。そもそも、彼氏・彼女なんて言うものほど定義があいまいなものは無いのだから困ったものである。
「まった?」と声をかけると、「ぜんぜん、」と笑って返してくる。その笑顔が、妙に中学生の時の山本武とリンクして不意に心臓が跳ねた。
私と山本武が、恋人同士だったのか、と聞かれると、中学生だった当時は全力で否定していたが、今となって考えてみれば恋人同然の付き合いをしていたのではないかと思う。好き、の『す』の字も出てこないような仲ではあったが、一週間に換算すると確実に目の前にいる彼よりも、当時武といた時間のほうが長かったし、密度も濃かったように思える。まぁ、学生と社会人という違いは確実にあるだろうが。
「さん?大丈夫ですか、」と少し幼い顔立ちの目の前の彼に顔をのぞきこまれた。いけない、いけない。また考え込んでいたようだ。ここまで今日の私の思考を支配するなんて、山本武、恐ろしい男だ。と一人心の中でくすりと笑いながら「大丈夫だよ。行こう、映画はじまっちゃう。」と彼をせかす。
「あ、さん、」
「ん?」
「今日メイクしてないんですね。」
おいおい、そこは突っ込んじゃいけないところだよ、青年。
映画は数年前に上映された映画のリバイバル上映だった。この映画で人気が出た若い男性俳優が演じる主人公が恋人を守るために戦うアクションもの。真新しくもなかったし、ベタすぎて笑いが出るというほどベタでもなかったが、まぁそれなりに楽しめた。
映画が終わり、喫茶店に入る。窓際の席に座り、私はまたティラミスを頼んだ。「さんそれ好きだね、」と目の前にいる彼は優しく笑う。『俺と、ケーキとどっちが好き?』なんて、野暮なことを聞かないから私は彼が好きだ。それは山本武もおんなじだった。『オレこと好き?』なんて、一度も聞かれたことはないし、私もそのようなことは一度も聞いたことがない。ただ、私が好きな物のことはよく覚えていて、『はこれだよな』と、私がまだ何も言っていないのに私がその時食べたいもの、ほしいものを当ててくるのが山本武だった。
「さん、また考え事?」
「え、あ、うん。」
すごい間抜けな顔してましたよ、と言う彼のおかしそうな顔が、また武と重なった。今日は武の日、なのかもしれないなぁ、とぼんやり思いながら運ばれてきたティラミスにフォークを刺す。食べ終わったらメイクをなおさなきゃ、と思って気がついた。今日はまだファンデーションすらつけていない。だからかもしれない、アイブロウとアイラインの違いさえ分からなかった幼いころのことばかり思い出してしまうのは。そういえば、初めて買った透明なグロスを初めてつけてみたとき、件の山本武に『、唇にはちみつついてるぞ』と大笑いされた苦い思い出がある。そのリップグロスは武に平手をお見舞いした後、ゴミ箱に捨ててしまった。
「さーん、またぼーっとしてますよ。」
「うえ!?」
「早く食べないと、俺がこのケーキ食べちゃいますよ?」
それは困る。慌ててティラミスにフォークを刺した、その時だった、ガシャンともパリンともつかない、乾いた大きな音がした。目の前をものすごい勢いで何かが通り過ぎる。慌ててそれを目で追うと、きれいに磨かれた床に転がっていたのは映画やドラマなどでよく見かける鉄の塊。音のしたほうに目をやると、床に落ちているそれがちょうど通り抜けたような穴があけられた窓ガラス。
「じゅ、銃弾!?」
そうはじめに声をあげたのは誰だっただろうか、不安な叫びは周りを巻き込んでどんどん大きくなる。
「銃弾?」「銃弾だって!?」「撃たれたの?」「誰が?」「どうすればいいの!?」「逃げろ!!!」「隠れろ!!!」「また撃たれるぞ!!」「いや!外に出ちゃダメだ!」「誰か助けて!!!」
静かだった店内は一瞬にして蜂の巣をつついたような騒ぎになった。荷物も持たずに外に飛び出すもの、パニックになり喚き散らすもの、地震でもないのにテーブルの下に隠れるものうろたえる私、眉間にしわを寄せる目の前の男。そして、店内だけではない、だんだん大きくなってくる店の外の喧騒は小さな穴しか開いていないガラス越しでも聞こえてきていた。
「まずいな、」
眉間にしわを寄せていた彼がそうつぶやいたのと、喫茶店の入り口が乱暴に開いたのはほぼ同時だった。大勢の黒服の男たちが私たちのほうへ近づいてくる、最初の衝撃から私はいまだに一ミリも椅子から動けていなかった
「さん、」
「え?」
「本当は乱暴なことはあまりしたくなかったんだけど…すみません、」
突如大きな衝撃が私を襲った。意識が遠のいていく。そんな中、私の頭に浮かんだのは、目の前にいる彼の顔ではなく、どこにいるのか分からない幼馴染の明るい笑顔だった。

「、何作ってんの?」
黒髪の少年が小柄な少女に声をかけた。。少女はにっこり笑って顔をあげて「花冠だよ」と答える。
「ふうん……」
少年は少女の流れるような手つきを食い入るように見つめる。そして「なぁ、」と再び少女に声をかけた。
「なぁに?」
「それ、オレにも教えて?」
少女は少し驚いたような顔をしてから「いいよ」とまたほほ笑んだ。
しばらくして、二人が「できた!」と叫んだのは同時だった。少女は大きな輪っかを少年の頭に乗せて、少年は小さな輪っかを少女の薬指にはめた。
「武のちっさいじゃん」
少女が自分の指にはめられたシロツメクサの指輪を見て唇を尖らせると「いいの。これは、けっこんゆびわだから」と少年は笑った。
「けっこんゆびわ?」
「そう」
少年は頷いてから「にあげる!」ともう一度笑う。太陽のように、青空のように、すべてを洗い流すように。
「わたしたちけっこんするの?」
「大きくなったらな!」
怪訝そうな顔で手作りの指輪を眺めていた少女の頬が次第に緩んでいく。
「ふうん、じゃ、やくそくね、」
「うん、ゆびきりな、」
絡まった二つの小さな小指は軽く数回揺れて離れた。

また昔の夢を見ていたようだ。今度は、今朝見た夢よりずっと小さいころの夢。今朝わいた疑問も、解決した。ごっこあそびだったけど、しっかり交わした約束。なのになんで忘れていたんだろう。幼い自分たちの照れくさくも懐かしい思い出につい頬が緩む。武は中学背の時までこの約束を覚えていたんだろう。だからあのときもあのようなセリフがでてきたんだ。『イタリアに行かなきゃいけないから、約束は守れない』って。そんなの、私が覚えていなかったら全然意味がないのに。横になって目を閉じたまま、私は声を出して笑った。
考え事をしている間に、だんだん思考がはっきりしてきた。ゆっくりとまぶたを開くとそこは薄暗い、倉庫のようなところだった。中身は何か分からないが大きな木箱が大量に積み重なっていた。体を起こすと、頭がズキンと痛んだ。どうやら、あの喫茶店で殴られて、気絶して、ここに連れてこられたらしい。なるほど、通りで見覚えのないところで寝かされてるわけだ、と一人納得し、こんなに非日常的すぎる事件なのに、意外に落ち着いてる自分に、これまた一人驚いていると、ガチャリと音を立てて倉庫の入り口が開いた。
「あ、さん、目が覚めたんですね」
そこにいたのは、先ほどまで私の目の前にいたあの男。喫茶店での彼の最後のセリフを思い出し、私は何歩か彼と距離を置く。やさしそうだ、と思っていたその笑みが、今は悪魔の微笑みのように感じられる。いやだ、いやだ、こないで!
「そんなに怖がらないでくださいよさん、俺はただ貴方にお願いがあるだけなんですから。」
「お願い……?」
「そう、」
男はますます笑みを深くする。にやり、と音がしそうなほどに。私は思わずごくりと唾を呑んだ。
「さん、山本武の情報、教えてください」
「お前らこれはどういうことだ?」
もみあげが特徴的な黒づくめの赤ん坊が、3人の成人男性をにらみつけながら銃を構えている。傍から見ればシュールな光景だが、そこに流れる殺気は本物だった。
「拳銃所持、おまけに発砲、挙句の果てには暴行で雨と嵐の隊員が日本の警察のお世話になってるらしいじゃねぇか。」
お前の責任だぞツナ、と赤ん坊……リボーンは三人の中でもひときわ小柄な青年の額に愛銃を突きつけた。ツナ、こと沢田綱吉は「オレ、何にも知らないんだけど!」と涙目になりながらホールドアップする。
「ま、まってくださいリボーンさん!」
「今回のはツナは全然関係ねーんだ!」
残りの二人……獄寺隼人と山本武が必死に綱吉を弁護する。それを見てリボーンは「やっぱりな、」と銃を下しどういうことだと二人に話を促した。(え!?オレ、脅され損!?)
「じつは……オレのところにコルーヴォファミリーが日本で活動を始めたという情報が入ってきたんです。」
「それはオレも知っている。情報筋は雲雀だろう?」
「はい」
話が進む中、綱吉が「ちょ、ちょっとまって!コルーヴォファミリーって何?」と疑問の声をあげた
「そんなこともしらねーのか。ダメツナ。」
「コルーヴォファミリーって言うのは、オレもヒバリに聞いてはじめて知ったんですけど、もともとはワインとかを取り扱ってる小規模なファミリーで、日本で活動を始めたのは焼酎なんかの日本酒を取り扱い始めたからだとか…」
「へぇ、そうなんだ……」
「ボスがそんなこと知らなくてどうするんだ」
リボーンの強烈な蹴りが綱吉の後頭部に炸裂し、彼は某戦闘民族のようだと揶揄される頭を抱えてうずくまる。「理不尽だ!」と叫んだその目尻には痛みからかうっすらと涙が浮かんでいた。
「で、そのコルーヴォファミリーがどうしたんだ?」
綱吉の叫びを無視して、話の軌道をもとにもどすようにリボーンが問いかける。
「はい、日本で活動を開始したコルーヴォファミリーを俺の部下が調査していたんですが……」
「……どうしたの?」
「……どうやら、幹部の一人がある人物に接触を図っているらしいって言う情報が入ってきたんです。」
「……ある人物?」
「……って誰?」
リボーンと綱吉の疑問の声に、獄寺は一瞬口を閉じて、言うべきか、言わないべきか思案しているような顔をした。そんな獄寺のことを山本が静かに呼ぶ。
「んだよ、」
「こっから先は、俺に話させてくんねえか?」
いつもならここで、『十代目に報告するのは右腕の仕事だ!』とか、『野球バカはすっ込んでろ!』と山本に出る幕を与えようとしない獄寺が、驚いたような顔をして「お前、それでいいのか?」と彼を気遣うようなセリフを吐いた。
「だいじょうぶだって、」
そう笑う彼の顔には、そこにいるすべての人たちを安心させる何かがあった。山本は小さく深呼吸して、ゆっくりと口を開いた。
「コルーヴォの幹部の『黒鴉』が接触を図っていたのは、なんだ。」
綱吉は空気の温度が数度ほど下がったような寒気を覚えた。
「山本武の、情報?」
「そう、」
私が言葉を繰り返すと、彼は満足そうに笑って頷いた。
「彼の弱点でも、住んでいる家でも、何でもいい。しってますよね?だって、さんは彼の幼馴染なんだし、」
「な、なんであんたが私とあいつが幼馴染って知ってんのよ!」
私がヒステリックに声を荒げると彼は「マフィアの情報網、舐めてもらっちゃ困りますよ。」とまた笑った。マフィア?なんでその単語がここで出てくるんだろう?
「あれ?その顔はもしかして……知らないんですか?」
「何、を?」
聞いちゃいけない、そう本能が告げていた。でも、わたしはそれを振り払った。彼の言葉への好奇心は隠せなかったから。だけど、次の瞬間、私は本能に従わなかったのを心の底から後悔することになる。
「山本武は、イタリア最強のマフィア、ボンゴレファミリーの雨の守護者。それの抹殺を企てているのが、コルーヴォファミリーの幹部であるこの俺。通称『黒鴉』です。」
改めて、以後お見知りおきを、と私の後輩だった黒鴉は頭を下げた。
「って……山本の幼馴染の!!??」
思わず叫んだ綱吉に「うるせえ」とまたしてもリボーンからの蹴りが入る。いつもは、そこで笑いの一つや二つ、起きるところだが、緊迫した場の空気はそれを許してはくれなかった。
「と黒鴉が接触を図っていて、それを獄寺が山本に伝えた。そういうことだな、」
リボーンの言葉に獄寺と山本がそれぞれ頷く。
「それで、に何かあったら困るから、俺の隊と獄寺の隊から一人ずつ、こっそり護衛をつけていたんだ。」
「賢明な判断だ。噂じゃ、黒鴉は自分の目的のためなら手段を選ばない男らしい。が女で一般人であろうが、何が起こるかわかんねぇしな。」
「で、でも……オレやリボーンに何か言ってからでもよかったんじゃ…」
「す、すみません十代目!!」
「ツナに…心配掛けたくなかったんだ。」
二人が辛そうな顔をするから、綱吉まで申し訳ない気分になってきて、「ううん、俺のほうこそ頼りなくてごめん、」と首を横に振った。
「謝ってる場合じゃねーぞツナ。どうして山本の幼馴染を護衛していただけで日本で撃ち合うことになったのか、説明してもらおうか。」
「あぁ。」
山本が返事をして、頷く。綱吉は口の中にたまった唾をごくりと飲み込んだ。
「これはオレも部下から聞いた話なんだけど、その時、黒鴉とは映画に出かけていてその帰りだったんだ。」
「わ、わけわかんない、マフィアとか、ファミリーとか、何かのお芝居?」
うろたえる私を見て、目の前にいる彼…黒鴉は「お芝居なわけないじゃないですか!」と大げさな反応を示した。
「さん、本当にあなた何にも知らなかったんですね。通りで警戒心も何もないと思いましたよ。あのときだって、ボンゴレの奴らが撃ちこんでこなかったらそのままあのケーキ、食べちゃってたでしょう?」
「え、ど、どういうこと?」
「やっぱり気付いていなかった。俺が薬、入れさせてもらってたんですよ。」
今日は特に注意散漫でしたからね、非常にやりやすかったですよ、と彼は笑う。うそにきまっている。頭の中の冷静な自分はそう言っていても、心では、この男の言っていることは本当なのではないだろうか、と思えてくる。それほどまでに、彼の話口調は人を信じさせるような説得力があった。
「さて、と。さん、どうして俺がここにあなたを閉じ込めたのかわかりますか?」
「分からないよ。わかるわけないじゃない!」
「まぁ、平和な日本で平和に暮らしてきた貴方ですからね。わからなくて当然です。いいでしょう、説明して差し上げます。」
黒鴉は笑う。私の反応の一つ一つが面白くてたまらないとでも言うように。
「さっきも言ったように俺はイタリアのマフィアであるコルーヴォファミリーの幹部です。ボンゴレファミリーの幹部、山本武の命を狙っています。彼のことを調べて行った結果、彼にかかわりの深い人物として挙がってきたのがさん、貴女です。」
「私…?」
「そう、俺達コルーヴォファミリーは貴女を拉致し、貴女を無事返すことを条件に山本武を呼び出し、彼を殺害する計画を立てていました。で、貴女が食べてるケーキに睡眠薬を入れさせてもらって、眠ったあなたをイタリアに連れてこようと思っていたわけなのですが、どういうわけか邪魔が入りましてね…」
まぁ、どうせボンゴレの手のものだとは思いますが、という彼の話を聞いて喫茶店での出来事を思い出す。彼の話を仮にすべて信じるとして、あの銃弾がボンゴレが・武がいる組織が、撃ちこんだのだとしたら、それはもしかして、私にティラミスを食べないようにと注意を促していたのだろうか?
「おそらく、貴女が考えているとおりですよさん。彼らは貴女を護るため、貴女を危険な目にあわせないためにあの銃弾を撃ち込みました。ま、そうだとしても、俺たちは無理矢理貴女をここに連れてきたんですけどね」
この男は私の考えていることが読めるのだろうか。気味が悪い。ここから逃げ出したい。だけど体が思うように動かない。
「あぁ、そろそろ薬が効いてきましたね。」
「くすり…?でも、私、ケーキは食べなかった…」
「貴女が眠っている間に吸引していただいたんですよ。暴れもしないし、抵抗もしないから非常にやりやすかった。」
「卑怯な奴…」
「なんとでも。マフィアとはそういうものです。……さてと、ドンボンゴレに電報でも打ちますかね、貴女の雨の守護者のお姫様が大変危険な目にあってますよ、ってね。」
武、武、ここにきてはダメだよ。この人は怖い人だよ。でも助けに来てほしいよ。
矛盾したことを考えていることは分かっていた。だけど私は、楽しそうに笑う黒鴉をただ黙ってみていることしかできなかった。
「なるほどな、お前らの部下が黒鴉がの食べていたケーキになにか薬を混入するのを確認して、独断ではあったが注意喚起のため発砲したところ、黒鴉の護衛達と乱闘になった、というわけか。」
リボーンが話をまとめ、山本が「あぁ、」と頷く。
「で、結局、奴らもも、騒ぎにまぎれてどこかへ消えてしまった……」
重い沈黙が訪れる。なんとか場の空気を和ませようと綱吉が口を開きかけたその時、彼のデスクの上の黒電話が大きな音を立てて着信を告げる。反射的に綱吉が受話器を取った。
「もしもし、………え!?……はい、はい……」
何度か応答し、彼は受話器を置いた。
「大変だ、コルーヴォファミリーがさんを監禁している」
「!」
部屋中に緊張が走る。そして綱吉は再び口を開いた。
「山本、俺たちが行かないと、彼女は殺されてしまうかもしれない」
黒鴉はドアの前に座って動かない。私は何もすることもできずに、ただ部屋の隅にうずくまっていた。どれくらいの時間が経っただろうか、薬の効果でいつの間にか眠っていたようだ。大きな爆発音で目が覚めた。
「やっときましたか、」
「な、なに、なんなの!?」
「さん、貴女のお迎えですよ。…とはいっても、貴女のところに来る前に家の者たちが始末する予定ですがね」
不法侵入、器物損傷、当然の報いです、と黒鴉は笑う。それよりもっと酷いことをお前はしているではないかと思ったが、そのように噛みつく気力はもう私にはなく、ただぼんやりと『これからどうなるんだろう』と考えるしかなかった。
ひときわ大きな爆発音と同時に、その部屋の扉は開いた。いや、開いたというのには語弊がある。『ぶっ壊された』。
「!!」
「え……武!?」
ずっとずっと、頭の中を占領していた男が目の前に現れた。突然のことに、驚いて言葉を失う。でも、困惑しているのは私だけではないようで、
「馬鹿な、ボンゴレがこの防壁を破ってここに来れるはずが……」
「ボンゴレ舐めてもらっちゃ困るぜ、ねぇ十代目」
「そうだね、思ったより簡単にたどり着けちゃってびっくりしたよ」
武に続けて沢田、獄寺、と懐かしい顔が壊れた扉から現れた。
「さてと、黒鴉、うちの雨の守護者の大切な人を誘拐したオトシマエって奴をつけてもらわなきゃ……俺もリボーンになぐられちゃうんだよね。だから…ごめんね?」
会わないうちにだいぶたくましくなっていた同級生たちがにっこり笑って武器を構えた。

「どうして、黙っていたの?」
の言葉に山本は何も言い返すことができずただ、「ごめん、」とつぶやいた。
「また謝る。」
「え?」
「あのときもそう、武は謝るばっかりで私に本当のことを話してくれないよね」
否定できなかった。いつも、に辛い思いや苦しい思いをさせたくなくて、真っ暗なこちらの世界に引きずり込みたくなくて、本当のことは言えないでいた。それでも、このようなことになってしまったのだから、それが正しい選択だとはとても言い難かった。「ごめん」とまた謝りかけて、自分の口を塞いだ。それでは意味がない、
「、どこまできいたんだ」
「何を?」
「俺のこと、俺たちのこと、」
「武はボンゴレファミリーの雨の守護者で、黒鴉が武の命を狙ってたってことくらいかな。」
「……それってほとんど全部じゃね?」
知られたくなかったことを知られてしまったことに対する焦りや訝しりはそんなになかった。心の奥底では、いつ書こう言う日が来ることを予想していたのかもしれない。
平日の昼間だったが、程よい気候のこの時期、南イタリアのオープンカフェで休息をとるビジネスマンは大勢いた。そのせいもあったのかもしれないし、ただたんに二人が大人になっただけなのかもしれないが、お互いに声を荒げることもなく、感慨の涙を流すこともなく、最後に並盛の喫茶店で過ごした時間の続きのように二人はそこに座っていた。あのときから変わったことといえば山本が頼む飲み物がメロンソーダからブラックコーヒーに代わっていたことくらいだった。
「は何がいい?」
「メニュー渡されても、私はイタリア語読めないんだけど。」
「あ、そっか。じゃ、俺がの好きそうなの適当に頼むな。」
そう言って山本はそばにいた店員を呼びとめる。その姿を見ては小さくため息をついた。
「どうした?」
「いや、なんで私、マフィアの幹部と呑気にお茶なんかしてるんだろうっておもって。」
「マフィアの幹部じゃねーよ。」
「いや、だって、そうなんでしょ?」
「そうじゃなくて、今のオレは、ただの山本武。の幼馴染だ。」
山本が笑ったその時、店員が彼が頼んだ商品を運んできての目の前に置いた。
「……これ、」
「さ、これ、好きだったよな?」
懐かしくて、嬉しくて、思わずも笑みがこぼれた。ココアがたっぷりのティラミスは、甘くてほろ苦い味がした。