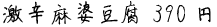駅前通りの角の中華料理店、本格的とはとてもいえない店主が見よう見まねで始めた小さな店だ。
それでも、その安さと家庭的な味を求めて客足が途絶えることは無い。夕方ともなれば、お腹をすかせた学生たちで店内はあふれかえっている。
そんな決してデートには向かないような店のカウンターで菅原と私は向かい合っていた。…もちろん、恋人同士としてではなくお客と店員として、だ。
*
菅原は私のバイト先であるこの店に月に2・3回訪れるちょっとした常連客だ。そして、私の学校の同級生である。私はバイトを初めて彼がはじめてこの店を訪れた時からそのことに気付いていたが、どうやら菅原はつい最近まで私が同じ学校の同じ学年に居ることを知らなかったらしい。
「バレー部、今度試合なんでしょ?がんばってね。」とか言うと、いつも不思議そうな顔をしていたのは、なんでこの中華料理屋の店員はうちのバレー部の試合の日程を知ってるんだろうと訝しがっていたのだろう。
店に忘れたマフラーを教室まで届けに行った時の彼の驚いた顔は今でも忘れられない。
それからというもの、彼の言葉から敬語が消え、下の名前で呼び捨てで呼ばれるようになり、それまで複数人で所謂店のピークの時間帯に店に来ることが多かったのが人が少ない時間帯に一人で来ることが多くなった。
その理由を「のこと年上だと思ってたし、それに部活のやつらとは学校の近くの駄菓子屋に行くことの方が多くなったんだよ」と彼はいつものように笑いながら語ったが、それが本当のことなのかどうか私は知らない。
*
今日も、お客がほとんど居なくなってかなりまったりとした閉店間際にがらがらと入口の引き戸を開けて暖簾をくぐって彼は現れた。
菅原が来るといつも、店主の奥さんが「ちゃんの彼氏が来たよ」とこっそり耳打ちしてくる。彼氏とか、そんなんじゃないのに。そう言い訳しても、奥さんは「いいから、いいから。」と私の手からまだ拭いている途中だった皿を引き取り、「彼氏とゆっくり話的な」とウインクする。そして、私をカウンターにひとり残して厨房にひっこんでしまうのだ。
だから、こうやってカウンターで菅原と向き合っているのは、不可抗力。決して私が望んだことではない。
そう私が思っていることを知っているのかは分からないが、菅原は椅子に腰かけながら「いつもの。」と注文する。
「いつもの、じゃわかりません。」
「えー、いつも同じの頼むんだから、わかるっしょ。」
イラついてる私の態度も気にすることなく、彼はニコニコと楽しそうだ。舌打ちをして、厨房に「麻婆!激辛!」と声をかけると奥さんに「すぐできるよ」と元気に言われた。奥さんも菅原の「いつもの」がわかってるみたいで、何とも言えない複雑な気分になる。
奥さんの言葉通りすぐに出てきたとほかほか湯気を立ててる麻婆豆腐が入った皿を、どん、置くと、彼は「いただきます」と律儀に手を合わせてから散蓮華を手に取った。
「そんなもの食べて、おうちのご飯食べられるの?」
「食べられるんじゃないかなあ。」
「いつもの駄菓子屋はどうしたのよ。」
「今日はこっちの気分だったんだよ。」
会話は長くは続かない。あとは、カウンターの内側に設置されたぼろぼろの椅子に腰かけてただひたすら菅原が口に散蓮華を運ぶのを眺めるだけだ。
食事を共にすることで、互いの仲が深まると言うのはよく聞く話だ。
私たちはべつに”共に”食事をしているわけではないし、べつに彼との仲を深めたいわけではないけれど、こうして何も喋らず彼が食事をするのを眺めている時間が嫌いではないということは確かだ。