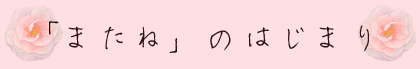さっきから、「月島くんは?」とばかり聞かれる。昔と同じだ。
1月の第2月曜日、成人の日である。周りは久しぶりの再開を喜ぶ声と、笑顔で溢れている。だが慣れないスーツに身を包んだ山口忠は、口角を緩めるような気分にはどうしてもなれなかった。
原因は、少し離れた地域の大学に行ってしまい今回の成人式に参加していない月島蛍にある。学生時代のほとんどを月島と共に行動していた山口に、彼のことを聞く人物があまりにも多すぎるのだ。そして、山口自身の名前は忘れられていることも多々。「そりゃ俺は、つっきーみたいに目立つ存在ではなかったけどさ。」声には出さないけれど、代わりに深いため息が出た。吐き出した空気は白く染まり、ふわふわと辺りを漂った。
「あれ、山口くん?」
ふわふわただよう白い水蒸気を見ていると、不意に名前を呼ばれた。振り返ると、華やかな紅い振袖を着た少女がそこに立っていた。…いや、成人した女性に少女というのは失礼だろうか。
「あ…えっと…。」
声をかけられたものの、彼女の名前が思い出せない。これでは先程まで月島のことを聞いてきた同級生たちのことを怒れない。
何も言えずにいると、彼女は「ああ!」と何かに気づいたような声を上げる。
「です。。」
「さんか!久しぶり。」
いかにも覚えていましたという風に挨拶をすると、も「久しぶりだね。」と笑顔で答えた。しかし、快く言葉を交わしたものの、また月島のことを聞かれるのかと身構えてしまう。
山口が何も言えずにいると、は「そうだ、」と思い出したように口を開いた。
「山口くんは今日の同窓会来る?」
「えっ、」
「あっ、もしかして同窓会のこと聞いていなかった?」
「いや、そうじゃないけど…。」
月島のことを聞かれなかった。ただそれだけなのに、何故か彼女が特別な存在のように感じる。人間の心理というものは単純なのか複雑なのかよく分からない。
「いくよ、同窓会。」
自然に、無意識のうちに、そう答えていた。「本当?」とが嬉しそうに目を見開く。
「うん、」
「よかった、楽しみにしてるね。」
そうして手を振り、は立ち去っていった。アップにした髪の毛についた金色の髪飾りがキラキラと眩しい。
そういえば成人式マジックという言葉を聞いたことがある。誰が言い始めた言葉なのかわからないが、成人式に久しぶりに会った男女は、お互いの大人になった姿を見て恋に落ちることが多いようだ。
雪が降り始めた。雪を見て最初に思ったことが「さん、寒くないかな。」だった自分にちょっと笑った。