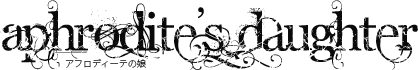ただ、彼に暖かい食べ物と、寝床を与えただけ。彼の名前さえ、私は知らない。知りたいとも思わない。ここにやってくる旅人はみんなそうだからだ。
町にいけば、無料で寝食ができるポケモンセンターがある。少額とはいえ金を払ってこんなすきま風のひどい山奥の宿に泊まりに来る人なんて、滅多に居なかった。
その上うちの宿はお人好しのばあちゃんがお金が無い人でもほいほい泊めてしまうから、経営はカツカツどころかぼろぼろだ。ばあちゃんが死んだらこんな宿売り払ってトレーナーになってバトルで賞金貯めて世界中をまわるんだ、なんて野望を抱きながら、今日も私は退屈そうに欠伸するブニャットを持ち上げ、椅子の上に下ろしてからデッキブラシで床を磨く。ばあちゃんが甘やかすから最近ますます太った気がする看板猫を横目で見て「あんたは気楽そうでいいね」と呟くと奴は『羨ましいだろう』とでも言うように鳴いた。まったく、腹がたつ。そこへ彼が「今日も仲がいいね」とくすくす笑いながら部屋から出てきた。そして「おはよう」とブニャットの頭をやさしく撫でる。
「やめてよ、そんなことをするとその子調子に乗るから」
「そんなことないよ、ねえ、ブニャット」
デブ猫は再び『どや鳴き』して、彼の手に頭をこすりつけた。それを見て彼も「トモダチだからね」とまた笑う。
彼がちゃんとお金を払ってここに泊まっているのか、ばあちゃんが得意のお人好しで泊めてやっているのか、それすら私は知らないが、何度かこうして顔を合わせて話をするうちに、彼はポケモンと話ができるのだ、と聞いた。嘘か本当か、たしかめる術は持ち合わせていないが、彼が居るとブニャットが楽しそうなのは確かだった。
「ブニャットはなんて言ってるの?」
そう聞くと彼は少し考えてから「たぶんこれを言ったら君は怒ると思うな」と言った。
「なにそれ、気になる」
「もう少ししたら教えてあげるよ」
彼はまた笑った。よく笑う人だ、とぼんやりと思う。
「それって、いつ?」
私の問いに彼は「そうだな、」と顎に手を当てて少し首を傾げた。ふわり、と揺れる緑色の長い髪がとても綺麗だ。
「僕と君がトモダチになってから、かな」
そう言って彼は先ほどブニャットを撫でたときのように私の頭を撫でた。そんな彼に少しだけイラっとして「何、言ってるの?」ときつい声を出してしまった。
「……嫌だった?」
「あ、ごめんなさい、そうじゃなくて」
彼が悲しそうな目をする。ちがう、そんな顔をさせたかったんじゃないんだ。私は思わず彼の手をとった。
「あなたと私はもう友達でしょう?」
彼は目を見開いて、驚いたような顔をした。そして、二、三度瞬きしてから「君は…」と口を開く。
「…君は、あの子に似てるね」
「……あの子って?」
不思議に思って聞くと彼は「あの子は…そうだな、強くて勇敢で英雄みたいな子だよ」と懐かしそうに答えた。
「私、そんなすごい人じゃないよ」
「そういうところも、そっくりだ。」
「意味わかんない」
私が唇をとがらせるのと、またブニャットが鳴いたのはほとんど同時だった。その声を聞いて彼は「あ、」と声をあげる。
「なに、」
「ブニャットが君のこと好きだって」
「…突然どうしたの」
「…だから、ご飯つくってほしいんだってさ」
まったく、現金なやつだ。そう思いため息をつくと、彼は「僕もおなかすいたな」と小さく呟いた。
「はいはい、何か作るから、ちょっと待っててくださいね。」
このいつ潰れるかわからない宿では、ゆっくりと時が流れている。ここが必要なくなるまでのほんの少しの間だけは、この流れに身を任せていてもいいかな、なんて、彼は思わせてくれるのだ。