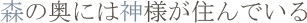それを初めて聞いたのはいつだっただろうか。神様を怒らせたら大変だから、森には行ってはいけないよ。昔からの言い伝え。深い意味や理由は考えたこともなかったが、森は不思議で恐ろしい場所という認識が村の子供たちの間に広まっていた。
その人は、見たこともないような銀色の鳥に乗ってここにやってきた。珍しい石を探しにきたのだという彼は、「エアームドだよ、」とその鳥を紹介して笑った。
「エアームドは何を食べるの?」
「どんな技が使えるの?」
「進化はしないの?」
好奇心から様々なことを矢継ぎ早に聞く小さな私に、彼は丁寧に答え、エアームドはそのたびに嬉しそうに羽を振るわせた。質問に答えた後、彼は決まって「キミはポケモンが好きかい?」と聞く。私が大きく頷くと、その人は彼の銀色の相棒と共にとても幸せそうな顔をするのだった。

「この森には、どんなポケモンが住んでいるんだい?」
それは、彼から私へのはじめての質問だった。嬉しくて、誇らしくて、自信満々に口を開きかけたときに気づく。
私は、あの森に住むポケモンのことを何一つ知らない。悔しくて、泣きそうになった。
「どうしたの?」
「どこかいたいの?」
「僕が何か気に障るようなことでも言った?」
そのすべてに私は首を横に振ってこたえる。今思えばとても面倒な子供だっただろう。
しばらく彼は何かを考えるような顔をしたり、彼は途方に暮れたような顔をしたり、困ったような顔をしたり、百面相をしていた。していたが、村の大人たちに呼ばれ、私に「少しだけ待っていてね」と告げてどこかへ行ってしまった。しかし、『待っていてね』と言われて待つようないい子では私は無かった。素早く左右を確認して、誰も自分のことを見ていないことを確かめてから、私は走りだした。

気づけば、森の奥深くまで来てしまっていた。もう、どちらに行けば帰り道なのか分からなくなっていた。それでも私はさみしくなどなかった。周りにはたくさんのポケモンたちがいたからだ。村にいる大人たちが連れていたものや、彼が連れてきていた者たちの名前しかわからなかったが、そこに居るポケモンたちはみな穏やかで、私を歓迎してくれているようだった。まるまるしたほっぺをこすりつけてくるもの、こちらをうかがうように興味深そうに見ているもの、さまざまだったが、一様にあいらしく、私はとても幸せだった。
「ちゃん!」
私を呼ぶ声がしたのはその時だった。振り返ると彼が慌てたような顔をして、こちらに駆けてくるのが見えた。
「ダイゴさん……」
「ちゃん、すごく心配したんだよ、」
「は、はい……」
「村の人たちもみんな君のことを探していた。」
「……」
『ごめんなさい』そう言おうとして、口を開きかけた、が、彼はそうさせてくれなかった。私の腕を引き寄せて、しっかりと抱きしめたのだ。
「ごめんね、僕があんなことを言わなかったら、森に入ろうなんて思わなかったよね。」
「そ、そんなことない…」
そう、そんなことはない、これはただの私のエゴ。彼に応えられなかったことが、くやしかっただけ。森に入る前と同じように、俯く私を、彼はまた困ったように見つめる。しばらくそうしていたが、彼は不意に「あ」と声を上げて、森の奥のほうを見た。
「ちゃん、あれ、見てごらん、」
彼が示した方向を見るとそこには小さな泉があった。水面にキラキラと光が反射している。
「近づいてみようか、」
彼の言葉に、私は頷く。そばまで来ると、それは更に美しく輝いて見えた。
中で泳いでいる水ポケモンたち。そして中央には一際美しくて大きい白いポケモン。
「ダイゴさん、あれは?」
「ミロカロス……だよ、僕も初めて見た。」
そうか、だから森にはいってはいけなかったんだね、と一人頷く彼に私は「どういうことなの?」と首を傾げ聞いた。
「ミロカロスはね、最高に美しいヒンバスが進化して誕生するポケモンなんだ。最高に美しいヒンバスには最高に美しい水が必要。……僕たち人間は水を汚してしまうからね、彼女たちを護るために、この森は立ち入ってはいけない場所になったんだろうね。」
そう言って彼は微笑んだ。
「じゃあ、神様って、あのミロカロス?」
「そうだね。もしかしたら、彼女の前にも彼女のお母さんや、おばあさんがここにはいたのかもしれないけれど、今の神様はきっと彼女だよ。」
「彼女って、ミロカロスは女の子なの?」
「うん。ひれが長いのがメス、短いのがオスなんだ。」
私が聞いたら何でも答えてくれる、そんな彼が好きだった。
それから長い間、私たちはそこに座り込んでたくさんの話をした。とはいっても、私が彼に質問して、彼がそれに応えるということの繰り返しだったけれど。
「ねぇ、ダイゴさん、」
「なんだい?」
「私、ここに来てよかった。こんなに素敵なものが見れたんだもの。」
そう言うと、彼は嬉しそうに私の頭をなでてくれた。
彼が連れてきていたエアームドが、僕のこともなでて、とでも言うように優しく鳴いた。

村に帰ると、私とダイゴさんはこっぴどく叱られた。いったい何をしていたのだ、と泣きながら私を抱きしめる母親や、黙ったままうつむいている父親を見て、私たちは顔を見合わせて苦笑いした。
彼らは何度も聞きたがったけど、私も、彼も、あの森であったことは、誰にも、一言も、話さなかった。話したくなかった。そうお互いに思っていることが何も口にせずとも分かっていたからだ。
あのとき以来、私はあの森の奥の泉には一度も足を運んではいない。また彼がこの村を訪れるその時まで、泉の奥深くでひっそりと暮らすミロカロスのように、心の中に大切に鍵を書けてしまっておきたかったから。
足元に、大きな影が落ちる。空を見上げると、銀色の大きな羽をもったポケモンがこちらに向かってはばたいてきていた。