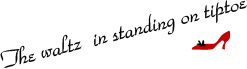「…即答かよ。」
ため息をつくアーサーに「だって無理なものは無理なんだもん」と唇を尖らせながら訴えると、「不細工」と呆れた顔で言われた。そんなのとっくの昔に自覚済みだ。
「ダンスはできるか?」と聞くのが唐突なら、「じゃあ、俺が教えてやる。」と言うのも唐突だった。私は思わず「は?」と馬鹿みたいな声をあげる。間抜け面も本日二回目だ。でも、次のアーサーの言葉により、私はさらに間抜け面をすることになる。
「お前、来月のパーティーに俺のダンスパートナーとして出ることになってるから」
アーサーはいつも唐突だ。
もう決定事項だからな、と念を押す彼に「え?」と返すことしか私にはできなかった。
「…もう、ダメ!無理!私ダンスなんかできないって!」
「できてもらわないと困るんだよ俺が!」
そんなことを言われたって出来ないものは出来ないのだ。私は高いヒールを履いてダンスしたため、地味に痛む足を擦りながら叫ぶ。「そんなに困るなら、ダンスが上手くて美人なお姉さんをつれてくればいいじゃない!なんで私なのよ!天下のアーサー様なら女の子の1人や二人、パーティーにお誘いするくらいおちゃのこさいさいでしょ!」
私の叫びを聞いて、一瞬驚いたような顔をしてから、彼は「…お前なぁ、」とため息をついた。床に座ってる私の目の高さに合わせてしゃがみ、それから私を抱き締めた。…え、抱き締めた?
「ちょ、なにするのよアーサー!」
暴れる私にはお構い無しに彼は耳元で「俺が、お前と、行きたいって言ってるんだよ。」と呟く。卑怯だ。私がこれをされたらアーサーのお願いを断れないこと、知ってるくせに。「それでも…来てくれねぇのか?」なんてかすれた声で聞かれたら、「行く」と答えるしかないでしょう?
「行く。行くよ、アーサーと。」
それを聞いて「よし」と立ち上がったアーサーの顔はすでに地獄のダンスコーチに戻っていた。
「わかったら大人しく練習しろ。これが躍れなかったら俺が恥をかくことになる。」
「…なんかうまく丸め込まれたような気がする。」
「何かいったか?」と睨まれ「なあんにも」と返す。なんだかんだ言っても、アーサーが好きだから、彼がどんなにわがままを言っても嫌いにはなれないのだ。
「なんで謝るんだよ」
「だってなんかすごい車だし…。それに、最近私のダンスの練習に付きっきりで仕事もあんまりできてなかったんじゃない?」
そう聞く私に「…そんなことねえよ」と目をあわせずに答える。そういうときのアーサーは大抵照れ隠しの嘘をついているということを私は知っている。
「嘘ばっかり。ドレスまで用意してくれちゃって…本当によかったの?」
「いいんだよ。」
目をあわせようとしないまま、アーサーは呟いた。「もとはといえば俺のわがままだし。」って。自覚はあったのか。
アーサーは話をそらすように「…ほら、ついたぞ。」と高級そうな建物が並ぶなかでも一等豪華な建物を示した。その前にゆっくりと音をたてず車が止まる。
「…どうしよう、アーサー。」
「あ?」
「想像していたよりずっと高級そうなところだよ。ねぇ、ここ、入るだけでお金とられたりしないかな?」
そう言うとアーサーは目をぱちぱちさせてからぷす、と小さく吹き出した。
「何バカなこと言ってんだ。ぼーっとしてないで、とっとと入るぞ。」
「う、うん。」
私が頷くとアーサーは自然な動作で「ほら、お手をどうぞレディ。」と手を差し出してきた。いつもの彼じゃないみたいで私はどぎまぎしながらその手をとる。「段差、気を付けろよ。」なんて言うその姿は本当に紳士のようで、普段の似非紳士っぷりからは想像もできないから、私は思わず「アーサーってすっごくかっこいいんだね」と呟いた。
「気づくの遅せえよバーカ。」
そう言って笑うのは私が知っているアーサーで、なんだか凄く安心して、思わず私もつられて微笑んだ。
ニヤリといたずらっ子みたいな笑みを浮かべながらアーサーは私を会場の隅の椅子までエスコートする。妙に板についているのが面白くて私はくすくす笑いながら「どーも」と椅子に腰かけた。
「ずいぶんうまくなったな」
「どっかの紳士さまが手取り足取り教えてくれたお陰だね」
そう言ってアーサーの顔を見ると「…よくわかってるじゃねーか」と照れ臭そうに頬を掻いた。滅多に私には見せない顔だからちょっと得した気分になる。
照れ隠しか「俺、飲み物とってくるけど…何がいい?」と聞くアーサーに「オレンジジュース。」と答えると「ガキ。」と馬鹿にしたように笑われた。
「うっさい。あ、アーサー、お酒はのんじゃだめだよ」
「うるさいのはお前だっての」
けらけら笑いながらその場を立ち去るアーサーの背中を見て、ふっと小さなため息をつく。アーサーのおかげでかなりほぐれていたとはいえ、結構緊張していたようだ。履きなれないヒールのせいで少し痛い足をぶらぶらさせていると、見知らぬ男性から「お嬢さん、」と声をかけられた。
「え、私?」
「そう、君ですよ。素敵なドレスをお召しですね。」
「ど、どうも…」
いつもツンツンなアーサーのそばにいるせいで誉められなれていない私はすぐにどぎまぎしてしまう。慌てる私を見ながら男性は楽しそうに笑って「どうです、是非、私と一曲…」と手を差し出してきた。だが、その手をとった…というよりも睨み付けながら強く握ったのは私ではなく、アーサーだった。
「悪いなジェントル、」
「あ、あなたは…カークランド公!」
またニヤリといたずらっ子みたいな笑みを浮かべ「こいつは俺の連れなんだ。悪いけど他を当たってくれ。」と言ってからアーサーは彼のてを振り払った。そして「し、失礼しました!」と謝る彼には目もくれず今度は私の手をとった。
「行くぞ、」
「あ、うん」
握ったその手は少し震えていた。
「アーサー、アーサー!どこまで行くの!?」
何度目かの呼び掛けでやっと「あ、わり…」と私の手を離し立ち止まった。会場の外は雨が降っていて、私もアーサーもびしょ濡れだ。ここがどこかもわからない。
「もう、ドレス汚れちゃったよ」
「……ごめん」
「せっかくアーサーにもらったのに……」
その先の言葉は続かなかった。アーサーにがっしりと両肩を捕まれたから。私の目を見て「なぁ、」という表情は私に「ダンスはできるか?」と聞いたときのそれと同じく真剣そのものだった。そんな彼にやはり私は「え?」と間抜けな返事しか返すことができない。「今日、楽しかったか?」何て聞かれて、ただただ頷くことしかできなかった。
「本当に?」
「…うん。なんか映画の主人公になったみたいだったし、アーサーの意外な一面も見れたし…楽しかった。」
アーサーはほっとしたようなやさしい顔をして「そっ、か」と笑った。私はアーサーのこの表情が好きだ。…まぁ、アーサーであればなんでも好き、というのが本当のところなんだけど。そんな彼に「ねぇ、アーサー、」と声をかけると「ん?」と返事がかえってきた。
「ここで映画だったら『じゃあもう一曲踊りましょうか』ってなるんじゃないの?」
そう聞くわたしの頭にアーサーは「ばーか。」とその拳を軽くぶつけた。
「映画じゃないんだからそんなことあるわけないだろ。俺は今日一日下手くそなお前にあわせてたから疲れた」
「ひどい!じゃあアーサーは楽しくなかったの!?」
「…それは…うん…まぁ、どうでもいいだろ」
アーサーがそっぽを向いて赤くなる。照れ隠しでそう言っているのはばればれだ。
「えー」と文句を言う私にさっきの男の人のように「ほら、帰るぞ」と手を差し出してきた。さっきと違うのは、その手を私が迷うことなくとったこと。目が合うと彼はとても嬉しそうな顔をした。
「最後までいなくていいの?」と聞く私に「…ま、なんとかなるだろ」といたずらっ子みたいに笑うこの人は、紛れもなく私の一番好きな人だ。