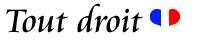「はいはい、今出ますよっと、」
誰に言うでもなくそう呟きながら、朝からうるさいお客様を迎えるために階下に降りる。寝間着のままだが、このようなことをする相手なんてあいつや、あいつくらいしか思いつかないからまぁ大丈夫だろう。
「どちらさま…」
ゆっくりドアを開けたのと、顔面にものすごいスピードで何かがぶつかってきたのがほぼ同時くらいだった。思わず「ぐほっ」と美しくない声を上げてしまう。
「ボンジュール、フランス。」
額をさすりながら顔を上げた俺に挨拶してきたのは、どうせ悪友であるトマト好きかじゃがいも好きだろうという予想に反して、ほっそりとした色の白い少女だった。
「……」
「昨日はお楽しみだったようね、」
はずかずかと家の中に乗り込んできて、飲んだままにしてあった空の酒瓶を見て眉間にしわを寄せた。彼女がやってくるときはたいてい俺が節操のないことをした後や、仕事に追いまわされて身の回りのことにまで手が回らなくなった時だった。そういうときにふらりとやってきて、俺の家をきれいに掃除した後二言三言説教して帰っていく。情けない姿しか見せていない自分に苦笑しかでてこない。今日も「それにしても飲みすぎよ」と瓶を眺める彼女に「まぁ誕生日だったわけだし、」と、言い訳することしかできなかった。
「あら、あんた誕生日だったの?」
「だったの…って、祝いに来てくれたんじゃないの?」
「まさか、あんたを祝うくらいならスペインまでトマトをいただきにいってるわ。」
手厳しい。だが、彼女が嘘をついていることは明白だ……と思いたい。去年も、一昨年も、この会話を繰り返したのだ。忘れているわけがない、というのは俺の勝手な想像だろうか。
「でもさ、」
だから俺は、ひとつの賭けに出る。俺だって男だ。彼女より少しでも有利に立ちたいと思うのは当然のことだろう?
「これ、俺にじゃないのかい?」
彼女の目の前に掲げて見せるのは先ほど己の顔にヒットした綺麗にラッピングされた袋。は少しうつむいて、「……それは…」と口ごもる。どうやら、投げつけたものをそのまま放置して帰るつもりだったようだ。
「たまたま…たまたまあんたの顔面にぶつけるのによさそうなハンカチと袋を見つけたからわざわざ時間を割いてぶつけに来てやったのよ。感謝しなさい。」
その言い訳も、少し苦しいんじゃないのかい?「……素直じゃないねぇ」と笑えば「私はいつだって素直よ。あんた以外に対してはね。」と返された。ごもっともだ。
やれやれ、と俺は肩をすくめた。このお姫様はいつも皮肉ばっかり言って、まったく思い通りになりやしない。どこかの眉毛が特徴的な島国を思い出すようだ。……ま、あいつに比べれば随分かわいいもんだけどな。
物思いにふけっていると、「ちょっとフランス、聞いてるの?」と彼女の拗ねた顔が目に入ってくる。
「もちろん、聞いてるよ。つまりこれは俺が誕生日プレゼントとしてもらってもいいって言うことだろう?」
にらんでくる彼女にウインクで返すと、その白い頬は見る見るうちに赤く染まった。
「あ、あんたがそうしたいんならそうすればいいじゃないの。」
消え入りそうな声で呟く彼女にもう一度「素直じゃないねぇ」と言って頭をなでれば、思いっきり手をつねられた。